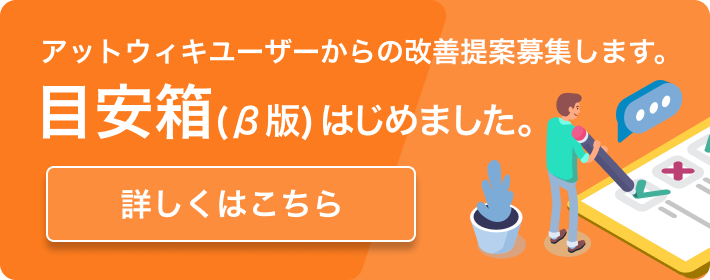「話が、あるんだ」
とある日、私は京介に、近所の人気の無い小さな公園へと連れ出された。
そして、そこで突然切り出された言葉。
京介の切羽詰った様子から、その『話』が、どれだけ深刻であるかが否応無く伝わってくる。
「……何かしら」
「…………俺なりに、ずっと考えてきたんだ。自分の気持ちを。『目先の答え』じゃない、『最後の答え』を」
耳に入ってきたその言葉で、一瞬のうちに私の動悸は跳ね上がった。
――『何のことに対する答えなのか』
そんなものは、考えるまでもなかったから。
……金縛りにあったように身体が硬直し、厭な汗が全身に噴出してくる。
思考が混濁し、視界が闇に閉ざされるかのような感覚を、下唇を噛んで必死に耐える。
――『これは、聞いてはいけない』
いつかのように、私の無意識が、私に警鐘を鳴らしていた。
「ま、待って。……お願いだから、それ以上は言わないで頂戴」
足りない酸素を振り絞って、擦れた声で懇願する。
「……頼むから、聞いてくれ。そうしなきゃ、俺たちはこれ以上前に進めない」
「……っ……聞かないと言っているでしょう……っ」
耳を塞ぎたい。この場から逃げ出したい。
しかし、私の意に反し、この現世の虚弱な体躯は一向に動いてはくれない。
駄目、どうにかして、止めさせないと――
「……っく……、どうしても話すというなら、私はこの場で死ぬわよ……っ?」
追い詰められた私は、いつかと同じ台詞を口にする。
我ながら、酷い脅し文句だとは思うけれど――実際に死にそうなくらいの負担が、今の私の心と身体に襲い掛かっている。
京介が言おうとしている『答え』を聞くことは、この体にとっては“死の宣告”と同じ。
だからこれは、脅しであっても“嘘ではない”のだ。
だが、一方の京介は、以前のように身じろぎはしなかった。
『そうくるだろうと思っていた』とでも言うように、その佇まいは落ち着き払っている。
そして、既に用意していたであろう覚悟を私に突きつけた。
「――お前が死ぬなら、俺も死ぬ」
「っ!?」
その口調も、表情も、怖いくらい完全に本気だった。
「……なっ、何を言っているの……」
「お前が死んだら俺も死ぬ! そんで来世まで追いかけて、そこでまたお前を捕まえて話をする!
そこでも死ぬっていうならそのまた来世だ! 何処までだって追いかけてやるってんだよっ! お前が何をしようが、俺はもう絶対逃げないからな!!」
一気に熱を帯びたその言葉。
来世という逃げ場すら、私から奪い去ってしまう。
……こうなってしまった京介は、もう誰にも止められない。けれど――
「……む、無茶を言わないで頂戴。それに……万が一あなたが死んだりしたら、桐乃はどうなるのよ」
「分からん。――いや、分かる、か。あいつと俺は同じだから。……あいつも死ぬさ。若しくは、“死んだも同然の状態になる”。全ては、お前次第だ」
駄目ね、これは。
――これはもう、逃げられない。
「…………酷い脅迫もあったものだわ。自分の命ばかりか、妹の命まで人質に取るなんて」
「お互い様だろ」
「……ふん、まあいいわ。……聞くだけは聞いてあげるから、言って御覧なさい」
……そう、ただ聞くだけ。聞くだけよ。
残念だけれど、京介の決断には意味などない。
『どちらを選んだとしても、既に私の答えは決まっている』のだから。
服の裾をぎゅっと掴み、京介の答えを待つ。
その時間は、刹那だったか、悠久だったか。よく分からない。
そうして、京介が口に出した『答え』は――
「黒猫。俺と――――結婚してくれ」
「──────!?!?」
――完全に、予想外の不意打ち。
いえ、勿論『どちらを選ぶか』という点については予想はしてしていたわよ?
でも、何かいろいろすっ飛ばした表現が、今の台詞には含まれていた気がするわ……っ?
「あ、ああ、あなたという人は……っ」
その動揺は、ゆっくりと憤怒の感情に変わっていく。
何をするにも、順序というものがあるでしょう。
だから私は、私の『理想の世界』の為に“儀式”を積み重ねてきたのだから。
今の京介の言葉は、京介にそのつもりが無くても、私の今までの行為を否定するもののように思えてしまったのだ。
「斜め上にも程があるわっ、最早狂気の沙汰としか思えないわね……っ。ふん、真面目に聞いた私が莫迦だった……わ……」
言葉尻が途切れる。
何故なら、私の“氷の視線《コキュートス》”で睨み付けた京介の表情が、私の罵倒にも一片も曇らず、真剣そのもの……だったから。
「…………本気、なの? 京介」
「ああ、本気だ」
それは、揺るがぬ意思。
……いいでしょう。どの道、言葉の意味なんてどうでもいいこと。
もっと大切なことは、他にあるのだから。
京介がその気なら、こちらもそれを確認させて貰うだけのことよ。
「……そう。……それで? “桐乃はどうするの”?」
「どうもしない。今まで通りだ」
返された言葉に、私は心底落胆した。
失望と、呆れと、苛立ちと、怒りとが入り混じって私の心を闇へと堕としていく。
「――話にならないわね。さっきのことは聞かなかったことにしてあげるから、金輪際あんな妄言を吐かないで頂戴」
踵を返し、その場を立ち去ろうとする私に、背後から投げ掛けられる声。
「待てよ。まだ話は終わってない」
「聞く価値もないわ」
「ああ、そうかもしれねえ。これから俺が言うことは、酷く自分勝手で、矛盾だらけの、俺自身の『理想の世界』の話だ」
『理想の世界』……その言葉に、私は踏み出した歩みを止めて、肩越しに京介を一瞥する。
「……お前の目指す『それ』とは違うのかもしれねえ。お前を……もしかしたら傷付けることになるかもしれない。
お前にとっては本当に無価値なものかもしれない。それでも……ずっと考えて出した、俺自身の『答え』なんだ」
……こんな、酷く切迫した様子の京介を、私は見たことがなかった。
いつも迷ってばかりで、へたれで、愚図で……その癖に妙に優しい人。
そんな優しい京介が、私を傷付けるかもしれないと言う。先程の言葉とは裏腹で、既に矛盾している。
あの言葉は、『私を選んだ』という意味ではない……ということなのだろうか。
私は京介に向き直り、その顔を正面に見据え、両手をスカートの前に組んで立つ。
私の“聞く意思”を感じ取ったのか、先輩はゆっくりとその決意の内を紡ぎだした。
「あれからずっと、考えてた。俺にとって『一番大切な気持ち』っていうのが何なのか。
“お前”を大切に想う気持ちなのか、妹を……いや“桐乃”を大切に想う気持ちなのか」
もう、京介の中には歪んだ硝子は無く――こうして桐乃への感情も素直に受け止められるようになっていた。
「でも、いくら考えても分からなかった。情けないけどな……俺にはどうやっても比べられなかった。
その気持ちはとてもよく似ているようで、でも全然違うものなんだよ。お前と桐乃が、違うように」
私と桐乃は、何もかもが正反対のようでいて、内面は実のところよく似ている……と、思うときがある。
桐乃は私の、私は桐乃の考えていることが、何となく分かってしまうから。
でも、京介はそんな私たちのことを、どちらかにどちらかを重ねることなく、ちゃんと一人一人の存在として見てくれている。
それが少し……嬉しかった。
「お前は桐乃じゃないし、桐乃もお前じゃない。当たり前のことだけどな。
俺の気持ちも同じだ。お前を想う気持ちも、桐乃を想う気持ちも、全然別のものだ。どっちも欠かせない、代わりにもならないものなんだ。
――――だったら、そんなの比べられるわけねえだろうが! 大小も優劣もない、どっちも俺には大切で、大事で、必要なものなんだよ!
へたれと言われようが、優柔不断と言われようが、俺にどっちかを選ぶなんてことは出来るわけねえんだよッ! くそぉぉ────!!」
京介の絶叫に、私は言葉を挟むことはおろか、瞬き一つさえ奪い去られてしまう。
「――それからまた考えたさ。じゃあどうすりゃいいのか。このまま『目先の答え』をずるずる引き摺って生きていくしかないのか?
ずっと悩んで、考えて……でも、あるとき気付いた。――答えは、ずっと前にお前らが教えてくれてた、って事に」
……私と、桐乃が……?
「どっちを選んでも後悔するなら、どっちも諦められないなら、足掻いて、欲張って、全力で『どっちも手に入れる』しかねえだろうが!
お前を大切に想う俺の気持ち、桐乃を大切に想う俺の気持ち、どっちも俺の大切な気持ちだ!
俺はどっちも大事にする。絶対だ! 誰が何と言おうが関係ねえ、俺の気持ちだ、俺が俺の気持ちを守って何が悪い!!」
京介のその心の叫びは、雷霆となって私を打ち貫いた。
正直、本当に心臓が止まるかと思ったくらい――。
それからどれだけの時間がかかっただろう。
私がようやく言葉を発することが出来るようになったのは。
「……よ、よ……よくもそんな恥ずかしい絶叫が出来るわね。……熱くなると暴走するのはあなたたち兄妹、本当にそっくりだわ」
「うぐっ……す、すまん」
京介も少し落ち着いたのか、いつものちょっとへたれた返事をする。
「とりあえず……京介の気持ちは分かったわ。……でも、それなら何故最初の発言になるのよ。私を選んだ、というわけではないのでしょう」
私も冷静さを取り戻し、先程の言葉に対する当然の疑問を投げ掛けた。
「桐乃は俺の妹だ」
「………………はい?」
その返答は、何の脈絡も無い言葉のように聞こえた。
時々、京介に私の言語が通じていないのかと思うときがあるけれど……、まだまだ同じ世界観を共有できていない、ということかしらね。
でも、それに続く言葉は、そんな生易しい幻想を一瞬で打ち消してしまう。
「じゃあ、お前は俺の何だ? もう恋人でもない、後輩でもない……ただの友達か?」
「……っ……、……それは……」
答えられなかった。
後輩だった私がいて、恋人だった私がいて……、それなら今の私は、何なのだろう。
ただの友達……いいえ、違うわね……『大切な』友達……?
それも違う気がする。
今まで考えたこともなかった……いえ、“努めて考えないようにしていた”ことだった。
でも、そんなことは――
「分かってるよ、肩書きなんて大した意味は無いってことは。
でもな、さっきも言ったけど、俺はお前も、桐乃も、どっちも大切なんだよ。ずっと一緒に居たいんだ。
それこそ、永遠に、来世までも」
京介はまた“来世”という言葉を口にする。それはきっと、京介にとって最上級の決意を表す形容詞なのだろう。
……ふん、一体、誰の影響かしらね。
「でも俺は不器用で、情けなくて、意気地なしで……またある日、お前が突然居なくなったりするような気がして。
そんなこと、もう絶対にないって分かってるつもりなのにな」
ずきっ、と、私の心の古傷が痛む。
確かに、もう二度とあんな真似はしないと誓ったけれど……過去に付いた深い傷は易々と消せるものではない。
私だけではなく、京介も、そしてきっと桐乃も……未だに心の奥にその傷を煩っているのだ。
「俺は“証”が欲しいんだよ。お前と繋がっているって思える、確かな“絆”が欲しいんだよ。
そしてそれは、俺と桐乃の血縁の絆と同等の、何より強くて決して切れない絆じゃなきゃ駄目なんだ――」
京介のいう“絆”は、きっと“呪い”。
「だから、黒猫。……いや、瑠璃。……俺と、桐乃と――――『家族』に、なってくれ」
そしてこれが、京介の“願い”。
京介の、『理想の世界』へ至る為の“儀式”。
“私と一緒になる”ではなく、“京介と桐乃と『家族』になる”という真意。
それが、あの言葉に秘められた、京介の導き出した『最後の答え』だったのだ。
「…………京介の『答え』の意味は、分かったわ。……ありがとう。とても……嬉しい」
真っ直ぐに私を見詰め、返事を待つ京介に、私は精一杯優しくそう言った。
本当に嬉しかった。こんな私を『家族に迎える』と言ってくれる人がいることが。
そしてそれが、私の最愛の人であることが。
でも、それでも、私は――
「でも……返事は出来ないわ。私には出来ない……。桐乃が、それを望んでいないかもしれないから……」
確かに、これは“私を選んだ”という結果ではなく、寧ろ今以上に“私と桐乃を同等にする”という真意がある。
でも、真意がどうあれ、京介に『伴侶』が出来るという事実に、桐乃は納得できるだろうか。
『恋人』とはその立場も、意味合いも、比べ物に――
「――あたしが何だって?」
不意にその場に響く第三者の声。
聞きなれたその声に振り返ると、そこに居たのは。
「き、桐乃……っ」
腕組みをした桐乃が私たち二人を見据えていた。
その表情は……訝しげなわけではなく、怒っているという感じでもなく……よく、分からない。
「……お前……俺たちの話、聞いてたのか……?」
「あんた声でかすぎだっての。んで?」
この反応、京介のほうでも桐乃がここに居ることは想定外、ということかしら。
そして、当然のように話の続きを私に急かす桐乃の様子からして、今の話は全部聞いていた……と思ってよさそうね。
こうなれば最早、私は現れた“裁決者《ジャッジメント》”に対して、覚悟を決めるしかなかった。
「……聞いていたなら話は分かっているでしょう。……あなたは、どう思っているの……?」
投げ掛けたその問いに下される審判は、糾弾か、拒絶か。
何を言われても、甘受するしかないわね――
「てかさ、黒猫あんた、今のプロポーズ酷いと思わないの?」
「……は?」
「『俺はどっちも好きだ、でも妹とは結婚出来ないからお前と結婚する!』って言われてんだよ? 人間として最低だよね?」
全く予想外の判決だった。……本当にこの兄妹は、時として私の想像の斜め上を行くわね。
とりあえず、ええと……これは私というより、京介が責められている……のかしら?
というか、物凄く曲解されているように思うのだけれど……。
「んなっ……そういう意味じゃねえ! お前ホントに俺の話聞いてたのか!?」
「怒鳴んないでよ、うっさいなァ。似たようなモンじゃん? っていうかアンタには聞いてないから、ちょっと黙ってて。
――それで、あんたはそんなんでいいの? “一生付いて回る問題”だよ? どう考えたって、“『普通の幸せ』なんて未来は無い”と思うケド?」
その妙なアクセントの台詞と、私の双眸を捉えて離さない桐乃の真摯な瞳から、私は一瞬でその言葉の真意を理解した。
――これは、“桐乃自身が探している『最後の答え』”を求めた問い掛けだ。
“兄”と“妹”――この絆の意味と、“京介”と“桐乃”の未来。
“絆”が“枷”になることも、この世界にはあるのだ。
今の私たちは、お互いを鏡に映して見ているようなもの――少なくとも桐乃は、そう見ている。私には、その確信があった。
それならば、私は全身全霊を賭けて答えなければならない。
それで、例え私の『理想の世界』が崩壊するとしても。
私の答えは、桐乃の答えと同等の意味を成すのだから。
“私”が“私”を否定することは出来ても、“私”が“桐乃”を否定することだけは、絶対に出来ないから。
「…………私は、京介のことが好きよ。ずっと前から、ずっと今まで。――それは……桐乃が、京介を好きな気持ちと、変わらないくらい」
「……うん」
「……でも、その気持ちと同じくらい、私はあなたが……桐乃が、好きよ。だから…………私は……っ」
そこで、言葉が詰まる。全身が震え、呼吸は荒く、息も絶え絶えだ。
京介の姿を一瞥し、そしてすぐに桐乃に向き直ると、……私は大きく深呼吸をして――『最後の答え』を言った。
「……私は、これからもずっと、あなたたちと一緒に居たい。一生、永遠に、来世までも。
その為になら……“『普通の幸せ』なんて要らないわ、……私は……『私たちの幸せ』が欲しいの”。
だから……だから、私は…………京介と、桐乃と…………『家族』に、なりたいわ」
「うん……うん、……ちゃんと『自分の』返事、できるじゃん。よく、頑張った」
今までに聞いたこともないような穏やかな声でそう言って、桐乃は私を胸元に抱き寄せる。
そして、慈しむように私の頭をそっと撫でた。
その優しい手のひらと、暖かい体温に、堰を切ったように私の瞳から涙が溢れてくる。
「…………うっ……ぐすっ……っぅ……」
「あんたが泣くなんて……ぐすっ……、初めて見たよ。……ばかじゃん、ここは喜ぶとこだって……ほらっ、ちゃんと元気出せっ……」
私を一層ぎゅっと抱きしめる桐乃。顔を埋めている私からは見えないその表情は、一体どのようなものなのだろうか。
桐乃はそうして、私が泣き止むまで、ずっと優しく頭を撫で続けてくれていた。
☆
「――それで、結局『お前は』どうなんだよ、桐乃」
どれだけの時間が過ぎただろう。
私たち二人の様子が一段落したと見て、京介が再び話題を戻す。
……本当に、雄というのは野暮で粗雑な生き物ね。全く……今のやり取りでどうして伝わらないのかしら。
「はぁ? 何言ってんの?」
それを聞いた桐乃も、心底呆れたような口調で返す。
そして、一瞬視線をこちらに投げた後――真っ赤に剥れて顔を逸らし、不貞腐れるような仕草で言い放った。
「アンタがこれ以上もたもたしてたら――――あたしが瑠璃と結婚してたっつーのッ!!」
――やや尖らせた口から繰り出されたのは、本日二人目からのプロポーズ。
それは、本当に先を越されて悔しがる子供みたいで。
一人目のそれよりも男気に溢れたその言葉に、私は軽く眩暈を覚え、倒れそうになる。
本当に……この“熾天使”は、どれだけ眩く、私を魅了すれば気が済むのだろう。
……クッ、この私としたことが、不覚にも…………惚れ直してしまったわ……。
☆
「大体さ、あんた、何であたしに先に相談しなかったの?」
帰り道、桐乃が京介に至極尤もな質問を投げ掛けた。
まあ、当然そう思うわよね。桐乃の承諾が先にあれば、京介自身もあれほど悩むことは無かったでしょうに。
「あたしが怒るとでも思ってたの? あたしが『たまたま』あそこに来なかったらどうする気だったの? バカなの? もう死んでいいよ?」
「うるせえなぁ」
矢継ぎ早に畳み掛ける桐乃を一蹴する京介。
桐乃の言う『たまたま』が少し気になるけれど、まあそこは今は言及しないでおいてあげましょう。
暫くして、京介は私と桐乃をそれぞれ一目した後、虚空を仰いで少し感慨に耽るように言った。
「……この事だけは、俺一人で考えて答えを出さないと意味がねえと思ったんだよ。
お陰で毎日毎日ずっと自問自答の繰り返し……まるで『俺が俺自身に人生相談』してる気分だったぜ――」
☆
――そして、幾つかの年月が過ぎ。
「おまたせ」
「おう、サンキュ」
「ひゃっほー! やっときたぁ」
既視感にも似た光景が、朝食を載せたトレイを持つ私を出迎える。
「ってか、やっときたぁ、じゃねーよ。今日の朝食は確か桐乃の当番だろ。なんで瑠璃が作ってんだよ」
「今日の夜は瑠璃が実家に行く用事があって遅くなるって言うから、あたしが当番代わったげたの」
「なん……だと……? ……ってことは今日の晩飯もカレーかよ……」
「うっさいなァ。ウチだってお母さん、カレーばっかだったじゃん。イヤなら別に食べなくてもいいケド?」
「そうよ。一応人間が食べられる物質が出来るようになっただけでも奇跡なのだから、神に感謝して食べなさい」
「出来るのはカレーだけ、だけどな」
「ぐぬぬ」
――『家族』になった私たちのやり取りも、相変わらずのこんな感じ。
変わったようで、何も変わらないようで。でも、一つだけ確かなのは、これからも私たちはずっと変わらないということ。
それが――何とも言えず心地よい。
これは、私の望んだ『理想の世界』なのかしら。それとも、京介の望んだ『理想の世界』なのかしら。
――いいえ、たぶん違うわね。
『理想の世界』なんていうのは、作り出すものでは無く。
自分と、自分の大切な人たちが、“自分たちを幸せだと感じたとき”、気付けばそこに在るような。
きっと、誰にでも当たり前に存在する世界なのだ。
-END-(家族の絆《エターナル・リンク》)
とある日、私は京介に、近所の人気の無い小さな公園へと連れ出された。
そして、そこで突然切り出された言葉。
京介の切羽詰った様子から、その『話』が、どれだけ深刻であるかが否応無く伝わってくる。
「……何かしら」
「…………俺なりに、ずっと考えてきたんだ。自分の気持ちを。『目先の答え』じゃない、『最後の答え』を」
耳に入ってきたその言葉で、一瞬のうちに私の動悸は跳ね上がった。
――『何のことに対する答えなのか』
そんなものは、考えるまでもなかったから。
……金縛りにあったように身体が硬直し、厭な汗が全身に噴出してくる。
思考が混濁し、視界が闇に閉ざされるかのような感覚を、下唇を噛んで必死に耐える。
――『これは、聞いてはいけない』
いつかのように、私の無意識が、私に警鐘を鳴らしていた。
「ま、待って。……お願いだから、それ以上は言わないで頂戴」
足りない酸素を振り絞って、擦れた声で懇願する。
「……頼むから、聞いてくれ。そうしなきゃ、俺たちはこれ以上前に進めない」
「……っ……聞かないと言っているでしょう……っ」
耳を塞ぎたい。この場から逃げ出したい。
しかし、私の意に反し、この現世の虚弱な体躯は一向に動いてはくれない。
駄目、どうにかして、止めさせないと――
「……っく……、どうしても話すというなら、私はこの場で死ぬわよ……っ?」
追い詰められた私は、いつかと同じ台詞を口にする。
我ながら、酷い脅し文句だとは思うけれど――実際に死にそうなくらいの負担が、今の私の心と身体に襲い掛かっている。
京介が言おうとしている『答え』を聞くことは、この体にとっては“死の宣告”と同じ。
だからこれは、脅しであっても“嘘ではない”のだ。
だが、一方の京介は、以前のように身じろぎはしなかった。
『そうくるだろうと思っていた』とでも言うように、その佇まいは落ち着き払っている。
そして、既に用意していたであろう覚悟を私に突きつけた。
「――お前が死ぬなら、俺も死ぬ」
「っ!?」
その口調も、表情も、怖いくらい完全に本気だった。
「……なっ、何を言っているの……」
「お前が死んだら俺も死ぬ! そんで来世まで追いかけて、そこでまたお前を捕まえて話をする!
そこでも死ぬっていうならそのまた来世だ! 何処までだって追いかけてやるってんだよっ! お前が何をしようが、俺はもう絶対逃げないからな!!」
一気に熱を帯びたその言葉。
来世という逃げ場すら、私から奪い去ってしまう。
……こうなってしまった京介は、もう誰にも止められない。けれど――
「……む、無茶を言わないで頂戴。それに……万が一あなたが死んだりしたら、桐乃はどうなるのよ」
「分からん。――いや、分かる、か。あいつと俺は同じだから。……あいつも死ぬさ。若しくは、“死んだも同然の状態になる”。全ては、お前次第だ」
駄目ね、これは。
――これはもう、逃げられない。
「…………酷い脅迫もあったものだわ。自分の命ばかりか、妹の命まで人質に取るなんて」
「お互い様だろ」
「……ふん、まあいいわ。……聞くだけは聞いてあげるから、言って御覧なさい」
……そう、ただ聞くだけ。聞くだけよ。
残念だけれど、京介の決断には意味などない。
『どちらを選んだとしても、既に私の答えは決まっている』のだから。
服の裾をぎゅっと掴み、京介の答えを待つ。
その時間は、刹那だったか、悠久だったか。よく分からない。
そうして、京介が口に出した『答え』は――
「黒猫。俺と――――結婚してくれ」
「──────!?!?」
――完全に、予想外の不意打ち。
いえ、勿論『どちらを選ぶか』という点については予想はしてしていたわよ?
でも、何かいろいろすっ飛ばした表現が、今の台詞には含まれていた気がするわ……っ?
「あ、ああ、あなたという人は……っ」
その動揺は、ゆっくりと憤怒の感情に変わっていく。
何をするにも、順序というものがあるでしょう。
だから私は、私の『理想の世界』の為に“儀式”を積み重ねてきたのだから。
今の京介の言葉は、京介にそのつもりが無くても、私の今までの行為を否定するもののように思えてしまったのだ。
「斜め上にも程があるわっ、最早狂気の沙汰としか思えないわね……っ。ふん、真面目に聞いた私が莫迦だった……わ……」
言葉尻が途切れる。
何故なら、私の“氷の視線《コキュートス》”で睨み付けた京介の表情が、私の罵倒にも一片も曇らず、真剣そのもの……だったから。
「…………本気、なの? 京介」
「ああ、本気だ」
それは、揺るがぬ意思。
……いいでしょう。どの道、言葉の意味なんてどうでもいいこと。
もっと大切なことは、他にあるのだから。
京介がその気なら、こちらもそれを確認させて貰うだけのことよ。
「……そう。……それで? “桐乃はどうするの”?」
「どうもしない。今まで通りだ」
返された言葉に、私は心底落胆した。
失望と、呆れと、苛立ちと、怒りとが入り混じって私の心を闇へと堕としていく。
「――話にならないわね。さっきのことは聞かなかったことにしてあげるから、金輪際あんな妄言を吐かないで頂戴」
踵を返し、その場を立ち去ろうとする私に、背後から投げ掛けられる声。
「待てよ。まだ話は終わってない」
「聞く価値もないわ」
「ああ、そうかもしれねえ。これから俺が言うことは、酷く自分勝手で、矛盾だらけの、俺自身の『理想の世界』の話だ」
『理想の世界』……その言葉に、私は踏み出した歩みを止めて、肩越しに京介を一瞥する。
「……お前の目指す『それ』とは違うのかもしれねえ。お前を……もしかしたら傷付けることになるかもしれない。
お前にとっては本当に無価値なものかもしれない。それでも……ずっと考えて出した、俺自身の『答え』なんだ」
……こんな、酷く切迫した様子の京介を、私は見たことがなかった。
いつも迷ってばかりで、へたれで、愚図で……その癖に妙に優しい人。
そんな優しい京介が、私を傷付けるかもしれないと言う。先程の言葉とは裏腹で、既に矛盾している。
あの言葉は、『私を選んだ』という意味ではない……ということなのだろうか。
私は京介に向き直り、その顔を正面に見据え、両手をスカートの前に組んで立つ。
私の“聞く意思”を感じ取ったのか、先輩はゆっくりとその決意の内を紡ぎだした。
「あれからずっと、考えてた。俺にとって『一番大切な気持ち』っていうのが何なのか。
“お前”を大切に想う気持ちなのか、妹を……いや“桐乃”を大切に想う気持ちなのか」
もう、京介の中には歪んだ硝子は無く――こうして桐乃への感情も素直に受け止められるようになっていた。
「でも、いくら考えても分からなかった。情けないけどな……俺にはどうやっても比べられなかった。
その気持ちはとてもよく似ているようで、でも全然違うものなんだよ。お前と桐乃が、違うように」
私と桐乃は、何もかもが正反対のようでいて、内面は実のところよく似ている……と、思うときがある。
桐乃は私の、私は桐乃の考えていることが、何となく分かってしまうから。
でも、京介はそんな私たちのことを、どちらかにどちらかを重ねることなく、ちゃんと一人一人の存在として見てくれている。
それが少し……嬉しかった。
「お前は桐乃じゃないし、桐乃もお前じゃない。当たり前のことだけどな。
俺の気持ちも同じだ。お前を想う気持ちも、桐乃を想う気持ちも、全然別のものだ。どっちも欠かせない、代わりにもならないものなんだ。
――――だったら、そんなの比べられるわけねえだろうが! 大小も優劣もない、どっちも俺には大切で、大事で、必要なものなんだよ!
へたれと言われようが、優柔不断と言われようが、俺にどっちかを選ぶなんてことは出来るわけねえんだよッ! くそぉぉ────!!」
京介の絶叫に、私は言葉を挟むことはおろか、瞬き一つさえ奪い去られてしまう。
「――それからまた考えたさ。じゃあどうすりゃいいのか。このまま『目先の答え』をずるずる引き摺って生きていくしかないのか?
ずっと悩んで、考えて……でも、あるとき気付いた。――答えは、ずっと前にお前らが教えてくれてた、って事に」
……私と、桐乃が……?
「どっちを選んでも後悔するなら、どっちも諦められないなら、足掻いて、欲張って、全力で『どっちも手に入れる』しかねえだろうが!
お前を大切に想う俺の気持ち、桐乃を大切に想う俺の気持ち、どっちも俺の大切な気持ちだ!
俺はどっちも大事にする。絶対だ! 誰が何と言おうが関係ねえ、俺の気持ちだ、俺が俺の気持ちを守って何が悪い!!」
京介のその心の叫びは、雷霆となって私を打ち貫いた。
正直、本当に心臓が止まるかと思ったくらい――。
それからどれだけの時間がかかっただろう。
私がようやく言葉を発することが出来るようになったのは。
「……よ、よ……よくもそんな恥ずかしい絶叫が出来るわね。……熱くなると暴走するのはあなたたち兄妹、本当にそっくりだわ」
「うぐっ……す、すまん」
京介も少し落ち着いたのか、いつものちょっとへたれた返事をする。
「とりあえず……京介の気持ちは分かったわ。……でも、それなら何故最初の発言になるのよ。私を選んだ、というわけではないのでしょう」
私も冷静さを取り戻し、先程の言葉に対する当然の疑問を投げ掛けた。
「桐乃は俺の妹だ」
「………………はい?」
その返答は、何の脈絡も無い言葉のように聞こえた。
時々、京介に私の言語が通じていないのかと思うときがあるけれど……、まだまだ同じ世界観を共有できていない、ということかしらね。
でも、それに続く言葉は、そんな生易しい幻想を一瞬で打ち消してしまう。
「じゃあ、お前は俺の何だ? もう恋人でもない、後輩でもない……ただの友達か?」
「……っ……、……それは……」
答えられなかった。
後輩だった私がいて、恋人だった私がいて……、それなら今の私は、何なのだろう。
ただの友達……いいえ、違うわね……『大切な』友達……?
それも違う気がする。
今まで考えたこともなかった……いえ、“努めて考えないようにしていた”ことだった。
でも、そんなことは――
「分かってるよ、肩書きなんて大した意味は無いってことは。
でもな、さっきも言ったけど、俺はお前も、桐乃も、どっちも大切なんだよ。ずっと一緒に居たいんだ。
それこそ、永遠に、来世までも」
京介はまた“来世”という言葉を口にする。それはきっと、京介にとって最上級の決意を表す形容詞なのだろう。
……ふん、一体、誰の影響かしらね。
「でも俺は不器用で、情けなくて、意気地なしで……またある日、お前が突然居なくなったりするような気がして。
そんなこと、もう絶対にないって分かってるつもりなのにな」
ずきっ、と、私の心の古傷が痛む。
確かに、もう二度とあんな真似はしないと誓ったけれど……過去に付いた深い傷は易々と消せるものではない。
私だけではなく、京介も、そしてきっと桐乃も……未だに心の奥にその傷を煩っているのだ。
「俺は“証”が欲しいんだよ。お前と繋がっているって思える、確かな“絆”が欲しいんだよ。
そしてそれは、俺と桐乃の血縁の絆と同等の、何より強くて決して切れない絆じゃなきゃ駄目なんだ――」
京介のいう“絆”は、きっと“呪い”。
「だから、黒猫。……いや、瑠璃。……俺と、桐乃と――――『家族』に、なってくれ」
そしてこれが、京介の“願い”。
京介の、『理想の世界』へ至る為の“儀式”。
“私と一緒になる”ではなく、“京介と桐乃と『家族』になる”という真意。
それが、あの言葉に秘められた、京介の導き出した『最後の答え』だったのだ。
「…………京介の『答え』の意味は、分かったわ。……ありがとう。とても……嬉しい」
真っ直ぐに私を見詰め、返事を待つ京介に、私は精一杯優しくそう言った。
本当に嬉しかった。こんな私を『家族に迎える』と言ってくれる人がいることが。
そしてそれが、私の最愛の人であることが。
でも、それでも、私は――
「でも……返事は出来ないわ。私には出来ない……。桐乃が、それを望んでいないかもしれないから……」
確かに、これは“私を選んだ”という結果ではなく、寧ろ今以上に“私と桐乃を同等にする”という真意がある。
でも、真意がどうあれ、京介に『伴侶』が出来るという事実に、桐乃は納得できるだろうか。
『恋人』とはその立場も、意味合いも、比べ物に――
「――あたしが何だって?」
不意にその場に響く第三者の声。
聞きなれたその声に振り返ると、そこに居たのは。
「き、桐乃……っ」
腕組みをした桐乃が私たち二人を見据えていた。
その表情は……訝しげなわけではなく、怒っているという感じでもなく……よく、分からない。
「……お前……俺たちの話、聞いてたのか……?」
「あんた声でかすぎだっての。んで?」
この反応、京介のほうでも桐乃がここに居ることは想定外、ということかしら。
そして、当然のように話の続きを私に急かす桐乃の様子からして、今の話は全部聞いていた……と思ってよさそうね。
こうなれば最早、私は現れた“裁決者《ジャッジメント》”に対して、覚悟を決めるしかなかった。
「……聞いていたなら話は分かっているでしょう。……あなたは、どう思っているの……?」
投げ掛けたその問いに下される審判は、糾弾か、拒絶か。
何を言われても、甘受するしかないわね――
「てかさ、黒猫あんた、今のプロポーズ酷いと思わないの?」
「……は?」
「『俺はどっちも好きだ、でも妹とは結婚出来ないからお前と結婚する!』って言われてんだよ? 人間として最低だよね?」
全く予想外の判決だった。……本当にこの兄妹は、時として私の想像の斜め上を行くわね。
とりあえず、ええと……これは私というより、京介が責められている……のかしら?
というか、物凄く曲解されているように思うのだけれど……。
「んなっ……そういう意味じゃねえ! お前ホントに俺の話聞いてたのか!?」
「怒鳴んないでよ、うっさいなァ。似たようなモンじゃん? っていうかアンタには聞いてないから、ちょっと黙ってて。
――それで、あんたはそんなんでいいの? “一生付いて回る問題”だよ? どう考えたって、“『普通の幸せ』なんて未来は無い”と思うケド?」
その妙なアクセントの台詞と、私の双眸を捉えて離さない桐乃の真摯な瞳から、私は一瞬でその言葉の真意を理解した。
――これは、“桐乃自身が探している『最後の答え』”を求めた問い掛けだ。
“兄”と“妹”――この絆の意味と、“京介”と“桐乃”の未来。
“絆”が“枷”になることも、この世界にはあるのだ。
今の私たちは、お互いを鏡に映して見ているようなもの――少なくとも桐乃は、そう見ている。私には、その確信があった。
それならば、私は全身全霊を賭けて答えなければならない。
それで、例え私の『理想の世界』が崩壊するとしても。
私の答えは、桐乃の答えと同等の意味を成すのだから。
“私”が“私”を否定することは出来ても、“私”が“桐乃”を否定することだけは、絶対に出来ないから。
「…………私は、京介のことが好きよ。ずっと前から、ずっと今まで。――それは……桐乃が、京介を好きな気持ちと、変わらないくらい」
「……うん」
「……でも、その気持ちと同じくらい、私はあなたが……桐乃が、好きよ。だから…………私は……っ」
そこで、言葉が詰まる。全身が震え、呼吸は荒く、息も絶え絶えだ。
京介の姿を一瞥し、そしてすぐに桐乃に向き直ると、……私は大きく深呼吸をして――『最後の答え』を言った。
「……私は、これからもずっと、あなたたちと一緒に居たい。一生、永遠に、来世までも。
その為になら……“『普通の幸せ』なんて要らないわ、……私は……『私たちの幸せ』が欲しいの”。
だから……だから、私は…………京介と、桐乃と…………『家族』に、なりたいわ」
「うん……うん、……ちゃんと『自分の』返事、できるじゃん。よく、頑張った」
今までに聞いたこともないような穏やかな声でそう言って、桐乃は私を胸元に抱き寄せる。
そして、慈しむように私の頭をそっと撫でた。
その優しい手のひらと、暖かい体温に、堰を切ったように私の瞳から涙が溢れてくる。
「…………うっ……ぐすっ……っぅ……」
「あんたが泣くなんて……ぐすっ……、初めて見たよ。……ばかじゃん、ここは喜ぶとこだって……ほらっ、ちゃんと元気出せっ……」
私を一層ぎゅっと抱きしめる桐乃。顔を埋めている私からは見えないその表情は、一体どのようなものなのだろうか。
桐乃はそうして、私が泣き止むまで、ずっと優しく頭を撫で続けてくれていた。
☆
「――それで、結局『お前は』どうなんだよ、桐乃」
どれだけの時間が過ぎただろう。
私たち二人の様子が一段落したと見て、京介が再び話題を戻す。
……本当に、雄というのは野暮で粗雑な生き物ね。全く……今のやり取りでどうして伝わらないのかしら。
「はぁ? 何言ってんの?」
それを聞いた桐乃も、心底呆れたような口調で返す。
そして、一瞬視線をこちらに投げた後――真っ赤に剥れて顔を逸らし、不貞腐れるような仕草で言い放った。
「アンタがこれ以上もたもたしてたら――――あたしが瑠璃と結婚してたっつーのッ!!」
――やや尖らせた口から繰り出されたのは、本日二人目からのプロポーズ。
それは、本当に先を越されて悔しがる子供みたいで。
一人目のそれよりも男気に溢れたその言葉に、私は軽く眩暈を覚え、倒れそうになる。
本当に……この“熾天使”は、どれだけ眩く、私を魅了すれば気が済むのだろう。
……クッ、この私としたことが、不覚にも…………惚れ直してしまったわ……。
☆
「大体さ、あんた、何であたしに先に相談しなかったの?」
帰り道、桐乃が京介に至極尤もな質問を投げ掛けた。
まあ、当然そう思うわよね。桐乃の承諾が先にあれば、京介自身もあれほど悩むことは無かったでしょうに。
「あたしが怒るとでも思ってたの? あたしが『たまたま』あそこに来なかったらどうする気だったの? バカなの? もう死んでいいよ?」
「うるせえなぁ」
矢継ぎ早に畳み掛ける桐乃を一蹴する京介。
桐乃の言う『たまたま』が少し気になるけれど、まあそこは今は言及しないでおいてあげましょう。
暫くして、京介は私と桐乃をそれぞれ一目した後、虚空を仰いで少し感慨に耽るように言った。
「……この事だけは、俺一人で考えて答えを出さないと意味がねえと思ったんだよ。
お陰で毎日毎日ずっと自問自答の繰り返し……まるで『俺が俺自身に人生相談』してる気分だったぜ――」
☆
――そして、幾つかの年月が過ぎ。
「おまたせ」
「おう、サンキュ」
「ひゃっほー! やっときたぁ」
既視感にも似た光景が、朝食を載せたトレイを持つ私を出迎える。
「ってか、やっときたぁ、じゃねーよ。今日の朝食は確か桐乃の当番だろ。なんで瑠璃が作ってんだよ」
「今日の夜は瑠璃が実家に行く用事があって遅くなるって言うから、あたしが当番代わったげたの」
「なん……だと……? ……ってことは今日の晩飯もカレーかよ……」
「うっさいなァ。ウチだってお母さん、カレーばっかだったじゃん。イヤなら別に食べなくてもいいケド?」
「そうよ。一応人間が食べられる物質が出来るようになっただけでも奇跡なのだから、神に感謝して食べなさい」
「出来るのはカレーだけ、だけどな」
「ぐぬぬ」
――『家族』になった私たちのやり取りも、相変わらずのこんな感じ。
変わったようで、何も変わらないようで。でも、一つだけ確かなのは、これからも私たちはずっと変わらないということ。
それが――何とも言えず心地よい。
これは、私の望んだ『理想の世界』なのかしら。それとも、京介の望んだ『理想の世界』なのかしら。
――いいえ、たぶん違うわね。
『理想の世界』なんていうのは、作り出すものでは無く。
自分と、自分の大切な人たちが、“自分たちを幸せだと感じたとき”、気付けばそこに在るような。
きっと、誰にでも当たり前に存在する世界なのだ。
-END-(家族の絆《エターナル・リンク》)