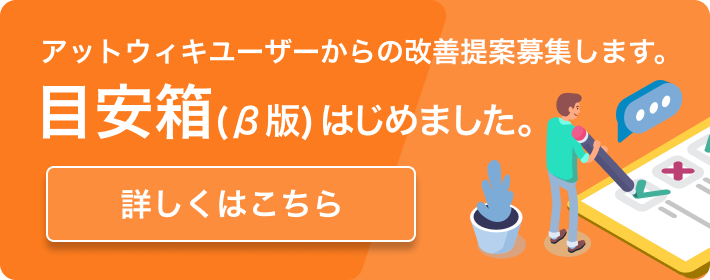2月14日。高坂邸にて。
「ただいま~」
「……おかえりなさい、先輩」
「……おかえりなさい、先輩」
帰宅した先輩を、玄関で出迎える。
本来、私は来訪者の立場なのだから「お邪魔しています」が正しいのでしょうけれど、この家に来る事も頻繁になって随分馴染んでしまったわ。
それに、こうして先輩を迎えるというのは、悪い気はしない――というより寧ろ、心地よい。
いつの日か、これが日常になる未来があるのなら……それはとても素敵な事だけれど。
本来、私は来訪者の立場なのだから「お邪魔しています」が正しいのでしょうけれど、この家に来る事も頻繁になって随分馴染んでしまったわ。
それに、こうして先輩を迎えるというのは、悪い気はしない――というより寧ろ、心地よい。
いつの日か、これが日常になる未来があるのなら……それはとても素敵な事だけれど。
「あれ、黒猫? どうしたんだ今日は」
今日の訪問の事は、先輩には伝えていなかった。急遽決まったことだったし、少し驚かせたいという気持ちもあったし。
いずれにしても、何かしら理由を付けて訪ねるつもりではあったけれど――今日という日は、やっぱり特別だから。
いずれにしても、何かしら理由を付けて訪ねるつもりではあったけれど――今日という日は、やっぱり特別だから。
「……あなたの妹に呼ばれたのよ。『バレンタインだから、大好きなお兄ちゃんにチョコ作ってあげたい!』って駄々を捏ねられて」
でも、そんな本心を隠し、少し嘲るような台詞を返すと。
「そっ、そんなこと言ってないでしょッ──!」
その私の言葉に瞬時に反応して、あの女がリビングから飛び出してくる。
……はぁ、全く、聞き耳を立てているくらいなら最初から一緒に出迎えればいいのに。こんな日くらい素直になれないのかしらね、この天邪鬼は。
……はぁ、全く、聞き耳を立てているくらいなら最初から一緒に出迎えればいいのに。こんな日くらい素直になれないのかしらね、この天邪鬼は。
「なるほど、さっきから気になってたこの甘い匂いはそういうことか」
「まぁ……最初はあやせと作って交換しようと思ってたんだケド、急に仕事が入っちゃったみたいでさァ」
「まぁ……最初はあやせと作って交換しようと思ってたんだケド、急に仕事が入っちゃったみたいでさァ」
その事情は私も最初に聞いた。けれども、多分、「誰と作るか」は大した問題ではないのよ。
あくまで、「兄の為に作る」というのが最大の目的なのだから。……この女は、口が裂けてもそんな事は言わないでしょうけれど、ね。
あくまで、「兄の為に作る」というのが最大の目的なのだから。……この女は、口が裂けてもそんな事は言わないでしょうけれど、ね。
「あやせの奴……うまく逃げたな」
「ん? ナンか言った?」
「い、いや別に。それで黒猫に白羽の矢が立ったわけか」
「そうらしいわね。……まぁ、折角の機会だし、チョコレートケーキでも焼いてみようかと思って」
「ん? ナンか言った?」
「い、いや別に。それで黒猫に白羽の矢が立ったわけか」
「そうらしいわね。……まぁ、折角の機会だし、チョコレートケーキでも焼いてみようかと思って」
正直に言えば、今年は生まれて初めて「手作りチョコ」なる“至高石《エリクシール》”を調合してみようかと思っていたのだ。
これまでバレンタインなんて、精々妹たちに小さなチョコレート菓子を買ってあげるくらいで、他人に義理でチョコを配ったことさえ皆無。
っふ、毎年この日は一日中、世に蔓延るバカップル共に「リア充は死ね」と怨念の呪詛を唱えていたものよ。
これまでバレンタインなんて、精々妹たちに小さなチョコレート菓子を買ってあげるくらいで、他人に義理でチョコを配ったことさえ皆無。
っふ、毎年この日は一日中、世に蔓延るバカップル共に「リア充は死ね」と怨念の呪詛を唱えていたものよ。
でも、今回ばかりは違う。こんな私にも『大切な人』が居て『伝えたい気持ち』がある。
圧倒的に経験不足とは言え、あらゆる情報を検索し、理論上はバレンタインの達人となったこの私に、あの女からの誘いは正に渡りに船。
高坂家のキッチンは器具が揃っているし、どうせなら自宅では作れないようなものを作ってみよう、と思い立ったのだ。
圧倒的に経験不足とは言え、あらゆる情報を検索し、理論上はバレンタインの達人となったこの私に、あの女からの誘いは正に渡りに船。
高坂家のキッチンは器具が揃っているし、どうせなら自宅では作れないようなものを作ってみよう、と思い立ったのだ。
「なるほどな。もう出来たのか?」
「丁度さっき完成したところよ。どうぞリビングへ。お披露目するわ」
「そんなに見たいの~? しょーがないなァ♪」
「丁度さっき完成したところよ。どうぞリビングへ。お披露目するわ」
「そんなに見たいの~? しょーがないなァ♪」
そう言って、妙にテンションの高い茶髪女と二人、先輩を甘い香りの漂うリビングへと誘う――
「じゃ~ん! どうよコレ! チョー可愛くない!?」
あの女がどや顔で差し出したチョコレートケーキは、自賛するわけではないけれど、それでも確かに見事な出来栄えだった。
形良く膨らんだスポンジに、チョコレートホイップの鮮やかなデコレーションと、様々に模られたチョコのトッピング。
見た目だけなら、商品として売っている物と遜色ないと言ってもいい。まあ、あの女が舞い上がるのも無理はないわね。
形良く膨らんだスポンジに、チョコレートホイップの鮮やかなデコレーションと、様々に模られたチョコのトッピング。
見た目だけなら、商品として売っている物と遜色ないと言ってもいい。まあ、あの女が舞い上がるのも無理はないわね。
「確かに、無駄に凝ってるなぁ。コレ二人で作ったの?」
「作ったのはほとんど私よ。あなたの妹は飾り付けしただけ」
「作ったのはほとんど私よ。あなたの妹は飾り付けしただけ」
……そうなのよね。私だってまさかここまで単独作業になるとは思っていなかったわ……。
却って、あの女に余計な手出しをさせないよう阻止するほうが大変だったくらいよ。
あのスイーツ2号が、口実を作ってこのイベントを回避した理由が、なんとなく理解出来てしまったわ。
却って、あの女に余計な手出しをさせないよう阻止するほうが大変だったくらいよ。
あのスイーツ2号が、口実を作ってこのイベントを回避した理由が、なんとなく理解出来てしまったわ。
「見た目が一番重要じゃん! 大体、このアタシが手伝うって言ってんのに一人で全部やっちゃうからさァ」
「……あなた、私が『じゃあチョコレートを湯煎して』と言ったら、いきなりチョコをお湯の中に放り込んだでしょう。その時点で諦めたわよ」
「あ、あれはっ、あ、あんたが『湯洗』なんて言うから……、あ、洗えばいいのかな~、と……」
「……あなた、私が『じゃあチョコレートを湯煎して』と言ったら、いきなりチョコをお湯の中に放り込んだでしょう。その時点で諦めたわよ」
「あ、あれはっ、あ、あんたが『湯洗』なんて言うから……、あ、洗えばいいのかな~、と……」
前々からその片鱗を覗かせてはいたけれど……この女、こと料理の方面については壊滅的に才能が無い。
大抵の事は人並み以上にこなすくせに、手先が不器用なのかしら。格ゲーとか見るも無残なものだし。
というか、器用不器用以前に、料理のセンス自体が常人と乖離している気がするわね……。何が「湯洗」よ、その発想は無かったわ。
大抵の事は人並み以上にこなすくせに、手先が不器用なのかしら。格ゲーとか見るも無残なものだし。
というか、器用不器用以前に、料理のセンス自体が常人と乖離している気がするわね……。何が「湯洗」よ、その発想は無かったわ。
「流石に、チョコレートを洗う人は初めて見たわ。――ふ、仕方ないわね。今度ミスドに行ったら、私があなたのチョコリングを洗ってあげようかしら」
「ぐ、ぐぬぬ……」
「ぐ、ぐぬぬ……」
フフッ、やはりこのマル顔には、ぐぬぬの表情が良く似合うわ。
さっきの苦労を差し引いても、これが見られただけで、今日往訪した甲斐があったというものね。
さっきの苦労を差し引いても、これが見られただけで、今日往訪した甲斐があったというものね。
☆
その後、切り分けられたケーキをそれぞれ食べ終えた私たちは、食後のコーヒーブレイクの準備を始めた。
先輩は、「美味いもんご馳走になったからな」と、お礼代わりにコーヒーを淹れてくれるということで、目下キッチンの戸棚を物色中。
私も、空いたお皿を片付けるため、先輩と一緒にキッチンへ移動していた。
あの女はと言うと、作ったケーキを美味しいと食べて貰えたのが余程嬉しかったのか、至極上機嫌にソファーで雑誌を読みながらにやにやしている。
先輩は、「美味いもんご馳走になったからな」と、お礼代わりにコーヒーを淹れてくれるということで、目下キッチンの戸棚を物色中。
私も、空いたお皿を片付けるため、先輩と一緒にキッチンへ移動していた。
あの女はと言うと、作ったケーキを美味しいと食べて貰えたのが余程嬉しかったのか、至極上機嫌にソファーで雑誌を読みながらにやにやしている。
――僥倖、というべきかしら。今こそ、今日、私がここへ訪れた“真の目的”を果たす、絶好の好機――
チョコレートケーキ自体は、単にあの女を手伝ったというだけ……私にとっては、訪問の大義名分に過ぎない。
先輩と二人きりで対面出来るシチュエーションを、ずっと待っていたのだ。
先輩と二人きりで対面出来るシチュエーションを、ずっと待っていたのだ。
「コーヒー豆……確かこの辺りにあったと思ったんだが……」
キッチンとダイニングを隔てるカウンターの下に蹲み込み、戸棚を探す先輩。
この千載一遇のチャンスを逃すわけにはいかない。躊躇う余地など、今の私には無かった。
この千載一遇のチャンスを逃すわけにはいかない。躊躇う余地など、今の私には無かった。
「……あの……っ、……先輩っ」
先輩のすぐ隣に、並んで屈む。
この位置だと、カウンターが壁になってあの女から私たちは見えない筈。声音も抑え目に、リビングに届かないよう気を遣う。
この位置だと、カウンターが壁になってあの女から私たちは見えない筈。声音も抑え目に、リビングに届かないよう気を遣う。
「ん? どうした、何か探し物か?」
「……こ、これっ……、……食べて、貰えるかしら……?」
「……こ、これっ……、……食べて、貰えるかしら……?」
それは、先のケーキ作りで余った材料で作っておいた、親指の先ほどの小さなハート型をしたチョコレート。
何の変哲も無い、銀紙に載せられたそれを、おずおずと先輩へ差し出す。
何の変哲も無い、銀紙に載せられたそれを、おずおずと先輩へ差し出す。
――此処からが、本当の“儀式”の始まり。
「可愛らしいチョコだな。このくらい一口で片付くぜ。お安い御用だ」
「っそ、……それじゃ、――ぱくっ」
「へ?」
「っそ、……それじゃ、――ぱくっ」
「へ?」
ありったけの想いと、精一杯の勇気を胸に、差し出したチョコを自らの口に含む。
「食べて」と言っておいてお前が食べんの? みたいな顔を先輩がしているけれど、気に留めている余裕なんてある訳がない。
そして、瞼をぎゅっと閉じ、勢いに任せて――
「食べて」と言っておいてお前が食べんの? みたいな顔を先輩がしているけれど、気に留めている余裕なんてある訳がない。
そして、瞼をぎゅっと閉じ、勢いに任せて――
「――んっ!?」
自らの唇を、先輩の唇へと押し付けた。
「……んっ……ちゅ……んむ……」
「…………ん、ぐ……」
「…………ん、ぐ……」
そして、含んだチョコを、舌を使って先輩の口唇に割り込ませる。
私の意図を察したのか、然したる抵抗もなく、小さなハートはすんなり先輩の口の中へ押し込まれた。
私の意図を察したのか、然したる抵抗もなく、小さなハートはすんなり先輩の口の中へ押し込まれた。
「……ん……っ、……ふぅ」
“儀式”を終え、触れ合う唇をそっと離す。
あらゆる意味で甘い接吻は、時間にすればほんの数秒、一瞬の白昼夢のような出来事だったけれど。
唇に残るほろ苦い甘さが、それが夢ではない確かな証拠だった。
あらゆる意味で甘い接吻は、時間にすればほんの数秒、一瞬の白昼夢のような出来事だったけれど。
唇に残るほろ苦い甘さが、それが夢ではない確かな証拠だった。
「もごもご……んぐ。――はぁ……流石にビックリしたぜ……」
「……えっと、その……い、厭、だったかしら……?」
「そんなわけないだろ。今まで食べたチョコの中で、一番、美味かった……というか、嬉しかった、か」
「そ、そう、……良かった」
「……えっと、その……い、厭、だったかしら……?」
「そんなわけないだろ。今まで食べたチョコの中で、一番、美味かった……というか、嬉しかった、か」
「そ、そう、……良かった」
言葉を交わすことで実感する余韻に、顔が火傷しそうなほど熱くなる。面映さのあまり、体中の血液が沸騰しているようだった。
もし、私自身がチョコレートだったら、その熱であっという間に溶けてしまうわね。
さすがに顔を見られるのが恥ずかしくて、俯いてしまう。
もし、私自身がチョコレートだったら、その熱であっという間に溶けてしまうわね。
さすがに顔を見られるのが恥ずかしくて、俯いてしまう。
「……今日はバレンタイン……大切な気持ちを伝える日だから」
顔は背けたまま、呟くように。それでも瞳だけは、上目遣いに先輩の顔を真摯に見つめて。
今日という日に、どうしても伝えたかったこと。
今日という日に、どうしても伝えたかったこと。
「私があなたに気持ちを伝えるなら……、やっぱり、“呪い《これ》”が一番……でしょう?」
それは、あなたに初めて私の気持ちを伝えた、大切な思い出を呼び起こす。
あれからどれだけ、苦悩と、覚悟と、葛藤と、決意とを積み重ねてきただろう。
言葉では伝え切れない――私の全ての“想念《おもい》”を込めた“呪い《キス》”。
あれからどれだけ、苦悩と、覚悟と、葛藤と、決意とを積み重ねてきただろう。
言葉では伝え切れない――私の全ての“想念《おもい》”を込めた“呪い《キス》”。
「――お前の呪いはいつも突然で、強力で……俺はもう完全に囚われちまってるみたいだな」
「……もしかして、私……先輩の枷になっている、かしら……」
「枷、とか言うなよ。これは、俺たち二人を繋ぐもの――『絆』っていうんだ。……お前はもう少し、自分に自信を持っていいと思うぜ」
「……もしかして、私……先輩の枷になっている、かしら……」
「枷、とか言うなよ。これは、俺たち二人を繋ぐもの――『絆』っていうんだ。……お前はもう少し、自分に自信を持っていいと思うぜ」
そう言った先輩の左手が、私の頬に触れる。ほんの少し力を入れたその掌が、私の背けた顔を先輩の正面に向かわせた。
「……っせ、先輩……?」
「お前なら知ってるよな。『呪い』っていうのは、そのまま術者に跳ね返ることもあるんだって――」
「お前なら知ってるよな。『呪い』っていうのは、そのまま術者に跳ね返ることもあるんだって――」
「――ねぇ~、コーヒーまだァ~?」
「っ!?」「うおっと!?」
「っ!?」「うおっと!?」
リビングからの不意の呼び掛けに、先輩も私も、文字通り飛び上がる。
っび、びび、吃驚したわ……。心臓が飛び出すかと思ったじゃない。
っび、びび、吃驚したわ……。心臓が飛び出すかと思ったじゃない。
「……あんたら、カウンターの陰でナニやってんの?」
え、えと、これはっ、その……別に疚しい気持ちがあって隠れていたわけではなくて……っ。
……そ、そう、“儀式”というものは、人目に付けばその効力を失ってしまうのよ。
大体、こ、こんなこと、人前で出来るわけがないでしょう。……こんな、恥ずか……あぁもう、察して頂戴っ。
……そ、そう、“儀式”というものは、人目に付けばその効力を失ってしまうのよ。
大体、こ、こんなこと、人前で出来るわけがないでしょう。……こんな、恥ずか……あぁもう、察して頂戴っ。
あの女の訝しげな声に、思いがけず狼狽してしまう。
そんな私を見兼ねてか、先輩が掩護の手を差し伸べてくれた。
そんな私を見兼ねてか、先輩が掩護の手を差し伸べてくれた。
「いや、こ、コーヒー豆が見当たらなくてな~。黒猫にも探してもらってたんだ」
「豆なら下の棚じゃないって。確か上の棚」
「お、おぅ。――あったあった。もうちょい待ってくれな」
「ったく、早くしてよね~?」
「豆なら下の棚じゃないって。確か上の棚」
「お、おぅ。――あったあった。もうちょい待ってくれな」
「ったく、早くしてよね~?」
特に機嫌を損ねた様子もなく、あの女はソファーに寝転んで、惜しげもなく露出させたその脚をぱたつかせている。
ふぅ、はぁ……。二、三回深呼吸して動悸を鎮める。本当、今ので確実に五年は寿命が縮んだわ。
それにしても、相変わらず傍若無人を地で行くわね、この家の女王様は。先輩は、あなたの下僕では無いのよ? ……それに近い気もするけれど。
でも、そんな二人のいつもの風景が、私の心で凪となり、ようやく平常の落ち着きを取り戻させてくれた。
ふぅ、はぁ……。二、三回深呼吸して動悸を鎮める。本当、今ので確実に五年は寿命が縮んだわ。
それにしても、相変わらず傍若無人を地で行くわね、この家の女王様は。先輩は、あなたの下僕では無いのよ? ……それに近い気もするけれど。
でも、そんな二人のいつもの風景が、私の心で凪となり、ようやく平常の落ち着きを取り戻させてくれた。
「……そこのニート、少しは働きなさい。私はこれから洗い物で手が離せないから、テーブルに人数分のカップを出して頂戴」
気を取り直してそう言う私は、妹たちに接する時と少し似た、毅然とした口調で。
「えぇ~、めんどくさいなァ……何でアタシが」
それに応じるあの女も、相変わらずの捻くれた調子で文句を返す。
これも私たちの“いつもの風景”。本当に手の掛かる“妹”を相手にしているような感覚に、自然と私の顔に微笑が零れてしまう。
これも私たちの“いつもの風景”。本当に手の掛かる“妹”を相手にしているような感覚に、自然と私の顔に微笑が零れてしまう。
渋々、といった感じで体を起こす茶髪女が、口を尖らせて嘯く。
「ったく、最近すぐお姉さん風吹かせちゃって……どうせなら妹ちゃん風にしとけってのよ……ぶつぶつ」
「何を訳の分からないことを言っているのよ。…………妹と言えば、ケーキの残りの半分は私がお土産で持って帰るから……
もしかしたら、ホワイトデーに妹たちからお返しが貰えるかも知れないわね?」
「(ФωФ)クワッ! コーヒーカップね! 任せといてっ!!」
「何を訳の分からないことを言っているのよ。…………妹と言えば、ケーキの残りの半分は私がお土産で持って帰るから……
もしかしたら、ホワイトデーに妹たちからお返しが貰えるかも知れないわね?」
「(ФωФ)クワッ! コーヒーカップね! 任せといてっ!!」
……効果覿面、という言葉が今ほど相応しいと思った場面は無いわね。
今までソファーに横たわっていたその怠惰な姿は一変し、あっという間に人数分のティーセットを揃えてしまう。
どうよ、と言わんばかりに腕組みをしてリビングに反り返るあの女。
呆気に取られる私の隣で、先輩が可笑しそうに、そして何処か嬉しそうに、顔を綻ばせた。
今までソファーに横たわっていたその怠惰な姿は一変し、あっという間に人数分のティーセットを揃えてしまう。
どうよ、と言わんばかりに腕組みをしてリビングに反り返るあの女。
呆気に取られる私の隣で、先輩が可笑しそうに、そして何処か嬉しそうに、顔を綻ばせた。
「――っくく、お前、ホント最近桐乃の扱いが上手くなったよな。なんか、普通に仲のいい『姉妹』みたいだぜ」
「……は、反応に困ることを言わないで頂戴……」
「……は、反応に困ることを言わないで頂戴……」
本当に反応に困るわ。
あの女と「姉妹になるってことの意味」、どれくらい理解しているのかしら……この鈍感なシスコン兄さんは。
あの女と「姉妹になるってことの意味」、どれくらい理解しているのかしら……この鈍感なシスコン兄さんは。
それとも、これが先輩の言う“呪詛返し”なのかしらね。本人に自覚が全く無いのが、困ったものだけれど――
-END-(バレンタイン・カース)