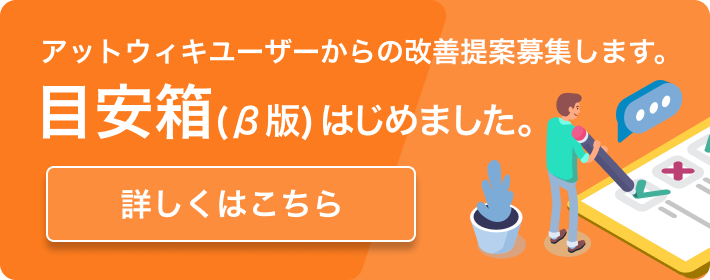茹だるような暑さの中、軒下に吊るした風鈴の音が耳に心地よい、そんな真夏の昼下がり。
「ふ~、食った食った。ごちそうさん」
俺は皿一杯に盛られていた昼食のそうめんを平らげ、満腹感に一息ついたところだ。
「はい、お粗末さまっ♪」
軽やかにそう答えたのは、キャミソールにホットパンツ姿、その上から可愛らしいエプロンを身に付けた美少女。
空いたお皿を重ねる仕草に、二本のお下げ髪がふわふわと揺れる。
歳相応に育った女の子らしい体躯だが、色香よりはまだ健康的な印象が先に来るような、笑顔の眩しい女の子。
空いたお皿を重ねる仕草に、二本のお下げ髪がふわふわと揺れる。
歳相応に育った女の子らしい体躯だが、色香よりはまだ健康的な印象が先に来るような、笑顔の眩しい女の子。
それは――“15歳になった日向ちゃん”の姿だった。
――と言っても、ここは数年後の未来ってわけじゃない。
細かい事情は省くが、ここは16歳の黒猫と、15歳の日向、14歳の珠希ちゃんが存在する世界。
まあ、俗に言う〝平行世界 〟ってやつだ。
更には、ここでは俺はその三姉妹の「義理の兄貴」ということになっていたりする。
以上、前作の説明終わり。
細かい事情は省くが、ここは16歳の黒猫と、15歳の日向、14歳の珠希ちゃんが存在する世界。
まあ、俗に言う〝
更には、ここでは俺はその三姉妹の「義理の兄貴」ということになっていたりする。
以上、前作の説明終わり。
まあそんなわけで、今は夏休みの真っ只中。
黒猫と珠希ちゃんは午前中からバイトに出掛けていて、家には俺と日向の二人だけ。
長期出張になっている両親から生活費は送られてきているのだが、兄妹4人を養うのはそれでも結構大変で。
黒猫と珠希ちゃんはアルバイトで家計を助けているってわけだ。親孝行な娘たちだよな、大したもんだ。
黒猫と珠希ちゃんはアルバイトで家計を助けているってわけだ。親孝行な娘たちだよな、大したもんだ。
何でその二人だけかと言えば、俺と日向は今年受験なので、進学するまでは学業優先でバイトは免除ってことらしい。
「片付けなら俺がやるぜ? 昼飯作ってもらったしな」
「ヘーキだよこのくらい。それに、作ったって言ったって、あたしじゃこんな簡単なものしかできないしさ」
「ヘーキだよこのくらい。それに、作ったって言ったって、あたしじゃこんな簡単なものしかできないしさ」
てきぱきとお皿を流しに運ぶ日向だが、何処となく申し訳なさそうな口振りだったりする。
と言うのも、両親が長期不在なため、当面の家事は兄妹で当番制。
料理に関しては基本黒猫がメインだが、日向や珠希ちゃんも週に1~2回は当番が回ってくるのだ。
料理に関しては基本黒猫がメインだが、日向や珠希ちゃんも週に1~2回は当番が回ってくるのだ。
そんな中、料理は大筋で何でもこなすが、メニューが和食寄りな黒猫と。
それに対するように、珠希ちゃんのほうは洋食のレパートリーを増やしつつある。
……ホント、黒猫を器用と言うなら、珠希ちゃんは多才と言うか。やたらスペック高いんだよなぁ。
それに対するように、珠希ちゃんのほうは洋食のレパートリーを増やしつつある。
……ホント、黒猫を器用と言うなら、珠希ちゃんは多才と言うか。やたらスペック高いんだよなぁ。
一方の日向は、今のところそれほど凝った料理は作れない。
性格が割と大雑把なせいか、あまり手の込んだレシピは不得手のようだった。
俺にしてみれば、立派に食えるモンが作れるだけ十分大したもんだと思うが……。
性格が割と大雑把なせいか、あまり手の込んだレシピは不得手のようだった。
俺にしてみれば、立派に食えるモンが作れるだけ十分大したもんだと思うが……。
だがどうやら日向はそのことを少し気にしているらしい。
「まぁそう言うなって。旨いモン食わしてもらった礼だ」
「え……、お、美味しかった?」
「おう」
「え……、お、美味しかった?」
「おう」
俺のその言葉に、日向は頬を赤らめてもじもじしている。
よく分からないが、やけに嬉しそうだ。
別にお世辞を言ったつもりは無いんだがな……実際旨かったし。
よく分からないが、やけに嬉しそうだ。
別にお世辞を言ったつもりは無いんだがな……実際旨かったし。
「お、お礼って言うならさ。片付けはいいから、後でちょっと……お願いがあったり……」
「ん、何だ?」
「その……、べ、勉強……見てほしいんだケド……」
「勉強?」
「ん、何だ?」
「その……、べ、勉強……見てほしいんだケド……」
「勉強?」
何だ、そんなことか。
思えば11歳のこいつも、よく宿題を教えてーってせがんできたっけ。
それを今更「お願い」とか、何を気兼ねしてるんだか。
思えば11歳のこいつも、よく宿題を教えてーってせがんできたっけ。
それを今更「お願い」とか、何を気兼ねしてるんだか。
「あっ、でも……キョウ兄ぃも自分の勉強あるし、忙しかったら別にっ……」
「アホか」
「アホか」
俺は、わたわたと手を振る日向の横に並び、その頭をくしゃっと撫でる。
「にゃっ?」
「お前が遠慮なんかする柄かっての。んなもん、お礼と言わずにいつでも見てやるって」
「ほ、ホントっ?」
「ああ。それ終わったらちゃぶ台のとこに勉強道具持って来いよ」
「……うんっ!」
「お前が遠慮なんかする柄かっての。んなもん、お礼と言わずにいつでも見てやるって」
「ほ、ホントっ?」
「ああ。それ終わったらちゃぶ台のとこに勉強道具持って来いよ」
「……うんっ!」
ぱあっと明るい笑顔になって、元気良く返事をする日向。
こいつ、“黒猫”の妹なのにどこか“犬っぽい”ところがあるんだよな。
こうやって構ってやると、反応が素直というか、すぐ表情に出るというか。
尻尾が付いてたらさぞぱたぱたと振られていそうだ。
こいつ、“黒猫”の妹なのにどこか“犬っぽい”ところがあるんだよな。
こうやって構ってやると、反応が素直というか、すぐ表情に出るというか。
尻尾が付いてたらさぞぱたぱたと振られていそうだ。
やっぱり日向はこうやって笑っていたほうがこいつらしい。
ま、たまには兄貴らしく、妹の面倒を見てやるとしますかね。
ま、たまには兄貴らしく、妹の面倒を見てやるとしますかね。
☆
後片付けを済ませ、日向が自分の部屋から教科書やらノートやらをお茶の間のちゃぶ台へ運んでくる。
何でわざわざここで勉強するのかというと。
――昭和の香りを色濃く残すここ五更家には、当然クーラーなんてものがあるわけもなく。
冷房器具は茶の間にある扇風機ひとつだけだからだ。
――昭和の香りを色濃く残すここ五更家には、当然クーラーなんてものがあるわけもなく。
冷房器具は茶の間にある扇風機ひとつだけだからだ。
まあ、元々俺もそれ程クーラーに頼ってたわけじゃないし、扇風機ありゃ上等だ。
逆にそっちのほうが集中できる位だな。
逆にそっちのほうが集中できる位だな。
「にゅふ、キョウ兄ぃに勉強見てもらうなんて、スゴイ久しぶりっ」
「そうだっけか?」
「そうだっけか?」
割と良く宿題を手伝わされている気がするが……って、そりゃ“日向ちゃん”のほうか。
この歳ともなるとちゃんと一人で頑張ってたのかね。感心感心。
この歳ともなるとちゃんと一人で頑張ってたのかね。感心感心。
「さて、何からやるか」
「うーん……、じゃあ数学からにしよっかな」
「うーん……、じゃあ数学からにしよっかな」
教科書を広げ、ぺらぺらとページを捲る。
おおぅ、ちゃんと中3の教科書だぜ。いや、この世界じゃ当たり前なんだけどね。
こうして改めて目の当たりにすると、その事実を実感するというか。
こいつももう受験生なんだよなぁ……。
おおぅ、ちゃんと中3の教科書だぜ。いや、この世界じゃ当たり前なんだけどね。
こうして改めて目の当たりにすると、その事実を実感するというか。
こいつももう受験生なんだよなぁ……。
ん? 受験といえば。
「そういやお前、高校どこ受けんの?」
ふと頭に浮かんだ質問を投げかけてみると。
「……え、えっと……、…………キョウ兄ぃと同じとこ……」
日向は一寸口籠もった後、少しだけ言い辛そうに答えた。
「弁展? ……自分で言うのも何だが、あそこ結構偏差値高いだろ。お前そんなに頭良かったっけ?」
うん、我ながら失礼な台詞だとは思う。
でも11歳のこいつは、夏休みの宿題を最後の三日間で泣きながらやるような、お世辞にも勤勉とは言えない子だったはず。
黒猫もよくそれで頭を悩ませていたっけなぁ……。
でも11歳のこいつは、夏休みの宿題を最後の三日間で泣きながらやるような、お世辞にも勤勉とは言えない子だったはず。
黒猫もよくそれで頭を悩ませていたっけなぁ……。
それとも、こっちの世界じゃ割と賢い子だったりするのか?
「う、うるさいなっ。……だからちょっとガンバってるんじゃん」
ちょっと剥れて、拗ねたような返事を返す日向だった。
……なるほど、どうやら頑張らないとヤバい程度には元のままのようだ。ちょっと安心したぜ。
安心というのも語弊があるが、あんまりイメージが変わっても困るしな。キャラ崩壊になりかねん。今更という気もするが。
安心というのも語弊があるが、あんまりイメージが変わっても困るしな。キャラ崩壊になりかねん。今更という気もするが。
まあ、何にせよ目標を持つのはいいことだと思う。
『目標を高く掲げ、自分自身が納得できるまで、それに向かって全力を尽くす』
――お前の姉ちゃんも、そうだったからな。
『目標を高く掲げ、自分自身が納得できるまで、それに向かって全力を尽くす』
――お前の姉ちゃんも、そうだったからな。
「ふむ。それじゃまあ、その頑張りを見せてもらうとするか」
「任せてっ! ……っと、チョットだけ待ってね」
「任せてっ! ……っと、チョットだけ待ってね」
俺の言葉を一旦遮り、日向は教科書の山の中から朱色の小さなケースを取り出す。
その蓋を開け、その中に納められていたある代物を取り出し、それを自らの両目に翳した。
その蓋を開け、その中に納められていたある代物を取り出し、それを自らの両目に翳した。
それは――人類の叡智が生み出した、至高の装具。
その名を、『眼鏡』――!
「……め……ッ、……眼鏡っ娘……だと……!?」
「ん? あれ、キョウ兄ぃの前でかけたことなかったっけ」
「お……お前、いつから……?」
「ん? あれ、キョウ兄ぃの前でかけたことなかったっけ」
「お……お前、いつから……?」
いつから、俺が眼鏡っ娘萌えだと知っていた……ッ!?
「最近だよ? ガンバりすぎちゃったせいか、少し視力が落ちちゃって……。でも、勉強するときだけだよ、かけるの」
「そ、そうか。そういうことか……ちょっと焦ったぜ」
「んにゃ? なんでアセるの?」
「いや、こっちの話だ。気にするな」
「そ、そうか。そういうことか……ちょっと焦ったぜ」
「んにゃ? なんでアセるの?」
「いや、こっちの話だ。気にするな」
一瞬、俺の嗜好を突いた精神攻撃かと思ったが、どうやら天然ものらしい。
この反応だと、俺の眼鏡属性はこいつには知られてはいないようだ。
この反応だと、俺の眼鏡属性はこいつには知られてはいないようだ。
ほっと胸を撫で下ろす。知らないならそれに越したことはない。
兄として、あまり妹たちに弱みを握られるのは芳しくないからな。
兄として、あまり妹たちに弱みを握られるのは芳しくないからな。
「ホントはコンタクトにしたかったんだけどさー。
キョウ兄ぃのことだから、どーせあたしが眼鏡かけると『地味だ』とか言うだろうし」
「いや! 眼鏡でいいッ! 眼鏡最高!!」
キョウ兄ぃのことだから、どーせあたしが眼鏡かけると『地味だ』とか言うだろうし」
「いや! 眼鏡でいいッ! 眼鏡最高!!」
思わず力説してしまったが、ここは断言せざるを得ない。
眼鏡こそ人類の至宝! コンタクトなど邪道の極み!!
眼鏡こそ人類の至宝! コンタクトなど邪道の極み!!
「わっ、ど、どーしたのっ。急に大声出してさ」
「あ、いや……その、何だ。眼鏡のほうが、お前には似合ってるよ」
「え……ホントに?」
「ああ」
「あ、いや……その、何だ。眼鏡のほうが、お前には似合ってるよ」
「え……ホントに?」
「ああ」
と、まあ、場を取り繕うために出た咄嗟の台詞ではあったが。
俺的眼鏡補正がかかっているとは言え、実際可愛らしい赤いフレームの眼鏡はこいつに良く似合っていた。
日向が言うほど地味な印象は無く、むしろお洒落なアクセサリーにすら見える。
これを選んだのが日向自身だとしたら、意外といいファッションセンスを持っているのかもしれない。
俺的眼鏡補正がかかっているとは言え、実際可愛らしい赤いフレームの眼鏡はこいつに良く似合っていた。
日向が言うほど地味な印象は無く、むしろお洒落なアクセサリーにすら見える。
これを選んだのが日向自身だとしたら、意外といいファッションセンスを持っているのかもしれない。
「……えへへ、そう言ってもらえると嬉しいな」
ほんのりと頬を朱に染めてはにかむ日向(眼鏡装備)。
うぐっ……こ、これは本当にやばい。何この眼鏡っ娘、反則的に可愛いぞ……!?
これがエロゲーのイベントシーンだったら、プリントスクリーン押して壁紙にしているところだ。間違いなく。
うぐっ……こ、これは本当にやばい。何この眼鏡っ娘、反則的に可愛いぞ……!?
これがエロゲーのイベントシーンだったら、プリントスクリーン押して壁紙にしているところだ。間違いなく。
にしてもあの地味猫が、まさかこんな隠し技を持っていたとは……。
とりあえず今はこいつが妹の立場で良かったぜ。そうでなければ自制が効かなかったかもしれん。
とりあえず今はこいつが妹の立場で良かったぜ。そうでなければ自制が効かなかったかもしれん。
「よーし、張り切って勉強するぞーっ!」
褒められて気を良くしたのか、日向は勢い良く広げた問題集に取り掛かった。
まずは余計な口出しはせずに、お手並拝見といこう。
まずは余計な口出しはせずに、お手並拝見といこう。
――それにしても、眼鏡といえばこの世界の俺は『秘蔵コレクション』を一体何処に隠しているんだろう。
ベッドの下か、押入れの奥か。和室だし、畳の裏という手もあるか? はたまた天井裏という可能性も……。
とにかく、後で確認しておかないとな。今度こそ、俺の尊厳は断固として死守せねばなるまい――!
ベッドの下か、押入れの奥か。和室だし、畳の裏という手もあるか? はたまた天井裏という可能性も……。
とにかく、後で確認しておかないとな。今度こそ、俺の尊厳は断固として死守せねばなるまい――!
と、人が勉強している隣でそんな不埒なことを考えているうちに、日向のほうは一通りの設問を解き終えていた。
問題集を受け取り、その答え合わせをする俺に、日向が自信なさげに問いかけてくる。
「……どう、かな」
「ふむ……。確かに、頑張った成果が顕著に現れているな」
「ふむ……。確かに、頑張った成果が顕著に現れているな」
算数の宿題でひーひー言っていた頃の日向ちゃんに比べたら、その差は歴然と見て取れる。
だが、それでも細かいところでのミスが目立ち、正直弁展に合格できるかと言えば微妙な線ではあった。
だが、それでも細かいところでのミスが目立ち、正直弁展に合格できるかと言えば微妙な線ではあった。
「……目標を持って頑張るのはいいことだと思うが、無理して弁展目指さなくてもいいんじゃないか?
別にそこじゃなくても、もっといい高校は他にいくらでもあるだろ」
別にそこじゃなくても、もっといい高校は他にいくらでもあるだろ」
つい、そんなことを口に出してしまう。
だがこれは、別に暗に諦めを促しているわけじゃない。
一言言っておかないと、こいつは自分の身体の限界を超えてまでも無理をしそうで心配になったからだ。
実際に、多少なりとも視力が犠牲になっているのは確かなんだし……。
だがこれは、別に暗に諦めを促しているわけじゃない。
一言言っておかないと、こいつは自分の身体の限界を超えてまでも無理をしそうで心配になったからだ。
実際に、多少なりとも視力が犠牲になっているのは確かなんだし……。
「……うん。自分でもさ、ちょっと厳しいかなとは思ってるんだけど……。でも、やっぱり弁展行きたいし」
「何でそんなに拘るんだ? 特別そんなにいいところでもねえぞ?」
「いいところとかじゃなくて……、キョウ兄ぃと同じ高校に行きたいんだもん」
「何でそんなに拘るんだ? 特別そんなにいいところでもねえぞ?」
「いいところとかじゃなくて……、キョウ兄ぃと同じ高校に行きたいんだもん」
……何とも単純な理由だった。
まあ、薄々そんな気はしていたが。
まあ、薄々そんな気はしていたが。
「そう言ってもらえるのは嬉しいが……、お前が来年弁展に入学したとしても、俺は今年で卒業になっちまうんだぜ?」
「うん……分かってるけど」
「あ、でも黒猫がいるか。あいつまだ一年だし、お前が入学してから2年は一緒に通えるな」
「……ルリ姉が、羨ましいな」
「ん?」
「だって、1年間だけだけど、キョウ兄ぃと一緒に学校に通えるんだもん」
「うん……分かってるけど」
「あ、でも黒猫がいるか。あいつまだ一年だし、お前が入学してから2年は一緒に通えるな」
「……ルリ姉が、羨ましいな」
「ん?」
「だって、1年間だけだけど、キョウ兄ぃと一緒に学校に通えるんだもん」
寂しそうに呟く日向。
例え同時期に通うことはできなくても、それでも俺の歩いていた道を追いかけたい、ということだろうか。
例え同時期に通うことはできなくても、それでも俺の歩いていた道を追いかけたい、ということだろうか。
「はぁ……、キョウ兄ぃが留年してくれれば一緒に通えるのにな……」
「縁起でもねえこと言うなよ。……まあ、何だ、高校は無理でも、大学なら一緒に通える時期もあるだろ?」
「えっ?」
「縁起でもねえこと言うなよ。……まあ、何だ、高校は無理でも、大学なら一緒に通える時期もあるだろ?」
「えっ?」
この世界での俺と日向は3歳違いだから、ストレートに行ったとして、四年制の大学なら1年間は一緒に通える計算だ。
「……そっか、大学まで行けばキョウ兄ぃに追いつけるんだ……」
「まあ、お前にその気があればの話だけどな」
「……うん。そうしたい。――そうなれたら、いいな」
「まあ、お前にその気があればの話だけどな」
「……うん。そうしたい。――そうなれたら、いいな」
少しだけ表情を明るくした日向の頭を、ぽんぽん、と軽く撫でてやる。
「……き、キョウ兄ぃ?」
「だったら、高校受験くらいで躓いてもらっちゃ困るな。仕方ねえ、ちゃんと合格できるレベルになるまで面倒みてやるよ」
「ほ、ほんと!?」
「おう。この成績優秀な先輩に任せとけ」
「だったら、高校受験くらいで躓いてもらっちゃ困るな。仕方ねえ、ちゃんと合格できるレベルになるまで面倒みてやるよ」
「ほ、ほんと!?」
「おう。この成績優秀な先輩に任せとけ」
大見得を切って胸を張る。
正直どう転ぶか分からないが、乗りかかった船だ。
まず教える側の俺が、自信の無い素振りを見せるわけにはいかないからな。
正直どう転ぶか分からないが、乗りかかった船だ。
まず教える側の俺が、自信の無い素振りを見せるわけにはいかないからな。
「……で、でも……キョウ兄ぃだって自分の受験勉強あるし、メイワクじゃ……?」
「だからそんな遠慮すんなってさっきも言っただろ? 俺は今更慌てて勉強しなくても十分合格圏内だっての。
それに、人に教えるっていうのも結構いい勉強になったりするんだぜ?」
「そ、それならいいケドっ。……キョウ兄ぃと一緒に勉強かぁ~、にゅふふっ」
「だからそんな遠慮すんなってさっきも言っただろ? 俺は今更慌てて勉強しなくても十分合格圏内だっての。
それに、人に教えるっていうのも結構いい勉強になったりするんだぜ?」
「そ、それならいいケドっ。……キョウ兄ぃと一緒に勉強かぁ~、にゅふふっ」
随分と嬉しそうな様子の日向を見て、俺はつい失笑を漏らしてしまう。
なんというか、遊園地に遊びにいく約束をした子供みたいな反応だったんだよ。
勉強するのがそんなに楽しみなのかね?
なんというか、遊園地に遊びにいく約束をした子供みたいな反応だったんだよ。
勉強するのがそんなに楽しみなのかね?
「むぐ……そ、それにしてもさ、キョウ兄ぃのクセに頭イイなんて、世の中オカシイよねっ。基本へたれなのにさーっ」
「お前な……前言撤回するぞ?」
「わっ、嘘ウソ! お願いします、先生っ!」
「お前な……前言撤回するぞ?」
「わっ、嘘ウソ! お願いします、先生っ!」
そんな俺に対してちょっとだけ憎まれ口を叩く日向だが、まあ半分は照れ隠しだろうから今回は大目に見てやろう。
「よーし、なんかすっごくやる気出てきたー!」
腕まくりをする真似をして、日向は再び問題集に取り掛かった。
どうやら、やる気は十分。……となれば、もう一押ししておくか。
どうやら、やる気は十分。……となれば、もう一押ししておくか。
「――そうだな、頑張って来年見事弁展に合格した暁には、お前の欲しいもの何でもひとつプレゼントしてやるよ」
後は、このやる気を持続させること。
モノで釣るというのもあざとい気がするが、それなりの効果はあるだろうからな。
モノで釣るというのもあざとい気がするが、それなりの効果はあるだろうからな。
「な、なな、何でもっ?」
「ああ。でも、俺の懐事情の許す範囲にしといてくれよ?」
「……そ、それなら、お金のかからないもので……ひとつお願い、しちゃおうかな……っ?」
「遠慮しなくていいんだぞ? 滅多にない機会なんだし」
「ああ。でも、俺の懐事情の許す範囲にしといてくれよ?」
「……そ、それなら、お金のかからないもので……ひとつお願い、しちゃおうかな……っ?」
「遠慮しなくていいんだぞ? 滅多にない機会なんだし」
普段は横柄に振舞って見えるが、こいつ性根は結構謙虚なのかね?
そんなら余計に、こんな時くらい多少の我侭も聞いてやりたくなるってもんだ。
そんなら余計に、こんな時くらい多少の我侭も聞いてやりたくなるってもんだ。
「うん、だから……一番欲しいもの、お願いしようかな……って」
「おう。何でも言ってみろ」
「おう。何でも言ってみろ」
お金のかからない、でも一番欲しいもの……ねぇ。
まあ本人がそう言うなら、俺は全力でそれを叶えてやるだけだが。
まあ本人がそう言うなら、俺は全力でそれを叶えてやるだけだが。
返答を待つ俺に対し、日向は大きく息を吸い込み、意を決するように言った。
「そ、それじゃっ……、あ、あたしが合格できたら、キョウ兄ぃと……き、キ……」
「き?」
「き?」
……何だ?
ぼっ、と顔を真っ赤にした日向は、口籠もって言葉尻を濁す。
お陰で、肝心なところが聞き取れなかった。
ぼっ、と顔を真っ赤にした日向は、口籠もって言葉尻を濁す。
お陰で、肝心なところが聞き取れなかった。
「すまん。もう一度言ってもらえるか?」
「……だっ、だから、……あたしに……キ、……キ……」
「……だっ、だから、……あたしに……キ、……キ……」
「――キス、ですか?」
…………。
「「 う わ あ ぁ ぁ ぁ ー ー っ ! ?」」
不意に割って入る、この場に存在しない筈の第三者の声に、俺と日向は文字通り飛び上がった!
見ると、いつの間にか日向の背後に見慣れたゴスロリ服姿が佇んでいる。
だが、服装は見慣れたものであっても、身に纏う少女は俺の記憶の中のそれとは違っていて。
だが、服装は見慣れたものであっても、身に纏う少女は俺の記憶の中のそれとは違っていて。
肩口に切り揃えられた髪、まだあどけなさの残る顔。
小ぢんまりとした背丈に、アンバランスな胸元の丸い膨らみ。
小ぢんまりとした背丈に、アンバランスな胸元の丸い膨らみ。
そこにいたのは、14歳に成長した“この世界の珠希ちゃん”だった。
「な、ななな、な……っ!」
「まったく、ちょっと目を離すと油断も隙もないですね、お姉ちゃんは。私たちの留守を狙って、兄さまにちゅーをねだるなんて」
「ち、ちゅー!?」
「うわーっ! うわーっ!? 何でもない、何でもないっ!」
「まったく、ちょっと目を離すと油断も隙もないですね、お姉ちゃんは。私たちの留守を狙って、兄さまにちゅーをねだるなんて」
「ち、ちゅー!?」
「うわーっ! うわーっ!? 何でもない、何でもないっ!」
大声を出す日向は、さっきよりも更に顔を上気させてじたばたと悶えている。
しかし『ちゅー』って……。流石の俺も一瞬驚いたが、珠希ちゃんは日向が俺にまさか『キス』をお願いするとでも思ったのか?
んなばかな。だって俺たち兄妹だぜ?
その証拠にホラ、日向もこんなに動揺してるじゃねえか。それだけ心外だったってことだろ?
んなばかな。だって俺たち兄妹だぜ?
その証拠にホラ、日向もこんなに動揺してるじゃねえか。それだけ心外だったってことだろ?
「て、てか珠ちゃんっ、帰ってきたなら『ただいま』くらい言ってよっ!」
「だって、お姉ちゃんが二人きりなのをいいことに兄さまを誘惑してるんじゃないかと思って、こっそり偵察を」
「し、してるワケないでしょー! ていうか珠ちゃんだけには言われたくないよ!?」
「ちゅーしようとしてたくせに」
「ししし、してないからッ!」
「だって、お姉ちゃんが二人きりなのをいいことに兄さまを誘惑してるんじゃないかと思って、こっそり偵察を」
「し、してるワケないでしょー! ていうか珠ちゃんだけには言われたくないよ!?」
「ちゅーしようとしてたくせに」
「ししし、してないからッ!」
……相変わらず、こっちの世界の日向と珠希ちゃんは張り合うなぁ。
まるで誰かさんたちを見ているようだ。
まあどっちにも言えることだが、別に仲が悪いってわけじゃなくて、どっちかっていうと子猫同士のじゃれあいって感じだが。
まるで誰かさんたちを見ているようだ。
まあどっちにも言えることだが、別に仲が悪いってわけじゃなくて、どっちかっていうと子猫同士のじゃれあいって感じだが。
「それにしても珠希ちゃん、随分早いな? いつもバイトは夕方までじゃなかったっけ」
傍観しているわけにもいかず、やんわりと横槍を入れてやる。
時計を見ると、まだ午後2時を廻ったくらいだ。
時計を見ると、まだ午後2時を廻ったくらいだ。
「今日は夕方からみんなでお祭りに行く予定じゃないですか。だから少し早く上がらせて貰ったんです」
あれ、そうなの?
言われてみれば、今日は近所で毎年花火大会がある日だったっけ。
言われてみれば、今日は近所で毎年花火大会がある日だったっけ。
「そういうわけでお姉ちゃん、いつまでも油売っていていいんですか?」
「へ?」
「今日のお買い物、お姉ちゃんの当番ですよね? 早く行ってこないと、出掛ける時間に支度が間に合わないんじゃないですか?」
「うわ、そうだった!」
「へ?」
「今日のお買い物、お姉ちゃんの当番ですよね? 早く行ってこないと、出掛ける時間に支度が間に合わないんじゃないですか?」
「うわ、そうだった!」
珠希ちゃんに言われて、日向はあたふたとちゃぶ台の上の勉強道具を片付け出す。
「あんまり急いで、眼鏡外し忘れるなよ?」
「わわっ」
「わわっ」
慌てて眼鏡を外し、ケースに仕舞う。
……俺が言わなきゃ、そのまま出掛けて行っただろうことは想像に難くない。それもアリっちゃアリだが。
……俺が言わなきゃ、そのまま出掛けて行っただろうことは想像に難くない。それもアリっちゃアリだが。
「眼鏡……?」
その言葉に反応し、珠希ちゃんが訝しげな声を漏らした。
「あれ、珠希ちゃんも知らなかったのか? 何か最近視力が落ちたとかで、勉強のときは眼鏡かけてるんだと」
「へぇ……そうなんですか」
「へぇ……そうなんですか」
何か思うところでもあるのか、珠希ちゃんは顎に手をやり、俺と日向の顔に交互に視線を投げる。
「……まさか、〝最終宝具 〟まで持ち出して兄さまを誘惑するなんて……。いよいよ本気で……?」
「へ? らぐな……って、何、またいつもの厨二病 ?」
「 何 で も な い か ら !! ほら、とっとと買い物行ってこい、な!?」
「わ、分かったから押さないでってば!」
「へ? らぐな……って、何、またいつもの
「 何 で も な い か ら !! ほら、とっとと買い物行ってこい、な!?」
「わ、分かったから押さないでってば!」
勉強道具を抱えた日向を、半ば強引に部屋の外へ押し出し襖を閉める。
その足音が自室のほうへ遠ざかっていったのを確認し、ほっと一息。
その足音が自室のほうへ遠ざかっていったのを確認し、ほっと一息。
というか、だ。
「 何 故 お 前 は 知 っ て い る !?」
「……ふふっ、この千葉の魔天聖〝聖猫〟の〝真眼〟を以ってすれば、兄さまの隠し事なんて全てお見通しです」
「……ふふっ、この千葉の魔天聖〝聖猫〟の〝真眼〟を以ってすれば、兄さまの隠し事なんて全てお見通しです」
……こ、怖え。正に適齢期の厨二病も然ることながら、この珠希ちゃんは何というか、底が知れない空恐ろしさがある。
そもそも、何処となく11歳のときとキャラが重なる日向に対し、珠希ちゃんは6歳のときとは全く違う。
今の珠希ちゃんは14歳に成長しているわけだから、そこには8年の歳月の経過があるわけで。
倍以上の年齢になっているんだから、性格や言動が一変していても不思議はない……といえばそうなのだが。
それにしたって……“どうしてこうなった”と言わざるを得ない……。
今の珠希ちゃんは14歳に成長しているわけだから、そこには8年の歳月の経過があるわけで。
倍以上の年齢になっているんだから、性格や言動が一変していても不思議はない……といえばそうなのだが。
それにしたって……“どうしてこうなった”と言わざるを得ない……。
「私が最後の手段として取っておいたのに……まさかお姉ちゃんに先を越されるなんて」
「……何を企んでいたのかは怖いから聞かないが、日向は別にお前が思ってるような効果を狙ったわけじゃないようだぞ?」
「そうみたいですね。……それなら、このことはまだ私と兄さまの二人だけの秘密、ってことにしておきましょうか」
「……そうしてくれると嬉しい」
「……何を企んでいたのかは怖いから聞かないが、日向は別にお前が思ってるような効果を狙ったわけじゃないようだぞ?」
「そうみたいですね。……それなら、このことはまだ私と兄さまの二人だけの秘密、ってことにしておきましょうか」
「……そうしてくれると嬉しい」
下手をすると公開処刑になりかねんからな。
ここは願ってもない提案を有難く受けさせて貰おう。
……しかし、よりによって一番知られたらまずい相手に知られてしまった気がする……。
ここは願ってもない提案を有難く受けさせて貰おう。
……しかし、よりによって一番知られたらまずい相手に知られてしまった気がする……。
そんなやり取りの中、先程日向を押し出した引き戸が再び開き、バッグを提げた日向がちらっと顔を覗かせた。
「それじゃ、ちゃちゃっと行ってくるケド……二人だけになってもヘンなことしたらダメだからね!」
「するかっ!」
「変なことって何ですか?」
「するかっ!」
「変なことって何ですか?」
釘を刺す日向に対し、ぽややんと天然口調で返す珠希ちゃん。
こういうときの珠希ちゃんは、厭味も邪気もまるで感じないから余計に始末が悪いんだよな……。
その証拠に、日向もそれ以上強くは言えず。
こういうときの珠希ちゃんは、厭味も邪気もまるで感じないから余計に始末が悪いんだよな……。
その証拠に、日向もそれ以上強くは言えず。
「と……とにかく! キョウ兄ぃ、お願いね!」
「分かったから、妙な心配してないでさっさと行ってこいっ」
「分かったから、妙な心配してないでさっさと行ってこいっ」
俺の言葉に、渋々といった感じで日向は買い物に出掛けていった。
――そうなると、この家に今度は珠希ちゃんと二人きり、ということになるわけだが。
日向にはああ言ったものの、正直嫌な予感しかしない。
日向にはああ言ったものの、正直嫌な予感しかしない。
天然珠希ちゃんはともかく、小悪魔モードの珠希ちゃんにどう対処していいのか。
ぶっちゃけ、未だに良く分からん。
果たして、俺の理性はどこまで耐えられるんだろう……。
ぶっちゃけ、未だに良く分からん。
果たして、俺の理性はどこまで耐えられるんだろう……。
「――それじゃ兄さま、私はお先にシャワーを頂いてきますね」
「し、しゃわー!?」
「し、しゃわー!?」
にわかに発せられたその単語に、つい過敏に反応して声色が裏返ってしまう。
くっ、我ながら情けないことこの上ない。
くっ、我ながら情けないことこの上ない。
「? 早くしないと、後で姉さまたちも使うでしょうし」
「あ、ああ……そうだよな。夕方から出掛けるんだったか」
「あ、ああ……そうだよな。夕方から出掛けるんだったか」
どぎまぎする俺に対して、珠希ちゃんはおっとりした調子で小首を傾げている。
い……いかんいかんっ。一体何を想像しているんだ、俺は。
これじゃ、単に俺が意識し過ぎなだけじゃねえか。
いくら魅力的な女の子に成長しているとはいえ、今の珠希ちゃんは妹なんだからな。義理だけど。
これじゃ、単に俺が意識し過ぎなだけじゃねえか。
いくら魅力的な女の子に成長しているとはいえ、今の珠希ちゃんは妹なんだからな。義理だけど。
平静を取り戻そうと大きく息を吐く俺に、ふと珠希ちゃんが耳元で囁く。
「……あの、兄さま?」
「ん?」
「……覗いちゃ、駄目ですよ?」
「覗くかッ!!」
「ん?」
「……覗いちゃ、駄目ですよ?」
「覗くかッ!!」
俺が平常心を保とうとしてる矢先にこれだよ!
これだから苦手なんだよ、“この珠希ちゃん”はっ!
これだから苦手なんだよ、“この珠希ちゃん”はっ!
「ふふっ。意気地なしですね、兄さまは♥」
くすくすと笑いながら、珠希ちゃんはお風呂場のほうへ去っていった。
くそっ、姉妹揃って似たような捨て台詞を吐きやがって。
意気地とか以前に、俺はお前の兄貴だっての!
……はぁ……、納得いかねえ……。
意気地とか以前に、俺はお前の兄貴だっての!
……はぁ……、納得いかねえ……。
☆
――その後しばらく、俺はお茶の間で勉学に勤しんでいた。
別に、珠希ちゃんに妙な誘惑をされたからじゃないぞ?
何かに没頭していれば、余計なことを考えずに済むからな。
一意専心、煩悩退散――。
別に、珠希ちゃんに妙な誘惑をされたからじゃないぞ?
何かに没頭していれば、余計なことを考えずに済むからな。
一意専心、煩悩退散――。
そのあまりの集中力に、引き戸が開かれた音にも気付かなかったくらいだ。
「あの……兄さま?」
掛けられた声に顔を上げると、いつの間にか珠希ちゃんが襖の横に立っていた。
集中していたせいか時間の経過が早く感じられるが、あれから既に小一時間が経過していたようだ。
集中していたせいか時間の経過が早く感じられるが、あれから既に小一時間が経過していたようだ。
シャワー上がりの珠希ちゃんは先程のゴスロリ服ではなく、白いブラウスとキュロットスカートといった部屋着に着替えている。
首に巻かれたタオルに触れる、まだ濡れた髪が少しだけ艶かしい。
首に巻かれたタオルに触れる、まだ濡れた髪が少しだけ艶かしい。
「ん、どうした。そんなところに突っ立って」
「その……ご一緒に風に当たらせてもらってもいいですか?」
「その……ご一緒に風に当たらせてもらってもいいですか?」
しおらしく訊ねてくる珠希ちゃん。
風……って、ああ、湯上りだから扇風機で涼みたいわけか。
そのくらい、いちいち断りを入れることもなかろうに。
そのくらい、いちいち断りを入れることもなかろうに。
「全然構わないぞ。つーか、そんなことで気ぃ使うな」
「……ふふっ、そうですね。ありがとうございます。兄さま♥」
「……ふふっ、そうですね。ありがとうございます。兄さま♥」
無邪気な笑顔を浮かべ、珠希ちゃんは俺の元へとやってくる。
それは何処となく、『ご本を読んでください』とせがんで駆け寄ってくる6歳の頃の姿に重なった。
それは何処となく、『ご本を読んでください』とせがんで駆け寄ってくる6歳の頃の姿に重なった。
こういうところが、やっぱり珠希ちゃんだと思わせるんだよな。
何だか少しほっとするぜ。
何だか少しほっとするぜ。
「兄さま、少し座を引いてもらえますか?」
「うん? ……こうか?」
「うん? ……こうか?」
そう言われて、俺は座っていた位置を座布団ごと少し後ろにずらす。
風に当たりたいなら扇風機のほうを動かせばいいものを……まあ別にいいけどな。
風に当たりたいなら扇風機のほうを動かせばいいものを……まあ別にいいけどな。
「それじゃ失礼して……ん、しょっ……と」
「んがっ!?」
「んがっ!?」
思わず素っ頓狂な声をあげてしまう俺。
だって、それも仕方ないだろっ。
珠希ちゃんは、当然といったように“俺の膝の上”にその腰を下ろしたんだから!
珠希ちゃんは、当然といったように“俺の膝の上”にその腰を下ろしたんだから!
「な、ななっ……なんでわざわざそこに座んの!?」
「何でって……兄さまが遠慮しなくていいって言ったんじゃないですか」
「何でって……兄さまが遠慮しなくていいって言ったんじゃないですか」
勿論、当の珠希ちゃんには悪びれた様子など微塵も無く。
「いや、言ったけどね!? それは扇風機に当たりたいって言うからでっ。てか、風に当たりたいなら扇風機を動かせばいいだろ!」
「駄目です。言いましたよね、『一緒に風に当たっていいですか』って。だから、兄さまも一緒に風に当たれるこの位置じゃないと」
「駄目です。言いましたよね、『一緒に風に当たっていいですか』って。だから、兄さまも一緒に風に当たれるこの位置じゃないと」
至極尤もらしいように言ってはいるが、屁理屈にしか聞こえねえ!
「それに、兄さまの膝の上は私の〝領域 〟って、幼い頃から決まっているんですよ? ふふっ」
た、確かに、6歳の珠希ちゃんは何かと俺の膝の上に座ってきていたが……っ。
三つ子の魂百まで、とは言うが、6歳の頃の習慣って14歳になっても続くもんなの!?
三つ子の魂百まで、とは言うが、6歳の頃の習慣って14歳になっても続くもんなの!?
いや、だからと言ってこれはマズいだろ!
あなた、黒猫姉妹の中で一番ちっちゃいけど、いわゆる“女の子パーツ”の発育だけは一番いいんですからっ!
こう、膝の上に感じるあったかくて柔らかい感触が、健康な男子にとっては物凄く危険なんです!
あなた、黒猫姉妹の中で一番ちっちゃいけど、いわゆる“女の子パーツ”の発育だけは一番いいんですからっ!
こう、膝の上に感じるあったかくて柔らかい感触が、健康な男子にとっては物凄く危険なんです!
「そっ、そうは言ってもだな……っ」
「きゃんっ。……あまり動かないでください、兄さま。くすぐったいです」
「きゃんっ。……あまり動かないでください、兄さま。くすぐったいです」
もぞもぞと体を動かしこの体勢から逃れようとしたが、珠希ちゃんの甘い声に阻まれてしまう。
つーか、動くと一層ヤバいことが分かった。
珠希ちゃんが膝の上で揺れる度、何というか……女の子特有のぷにっとした弾力が直に伝わってきて……!
つーか、動くと一層ヤバいことが分かった。
珠希ちゃんが膝の上で揺れる度、何というか……女の子特有のぷにっとした弾力が直に伝わってきて……!
「ちょっと涼むだけですから。その間だけ……駄目ですか?」
珠希ちゃんは、座った姿勢のまま顔だけ振り返り、上目遣いで背後の俺を見上げてそう懇願する。
湯上りで火照った表情。その中で真っ直ぐに俺を見つめる、潤んだ二つの瞳――。
湯上りで火照った表情。その中で真っ直ぐに俺を見つめる、潤んだ二つの瞳――。
くっ、何て強力なおねだり攻撃なんだ……!
可愛い妹にこんな顔をされたら……シスコンの俺が断れるわけないだろ!
可愛い妹にこんな顔をされたら……シスコンの俺が断れるわけないだろ!
「わ、分かったよ。……少しの間だけだからな」
「ふふっ、ありがとうございます、兄さま……♥」
「ふふっ、ありがとうございます、兄さま……♥」
そう言って、珠希ちゃんは安心したように俺の胸にその背中を預けてきた。
薄布を通じて伝わってくる温まった体温と、柑橘系のシャンプーの香りが、俺の五感を擽る。
涼むどころか、余計に熱が上がる気がするんだが……、そう思うのはまた俺が意識し過ぎなせいなのかね……。
涼むどころか、余計に熱が上がる気がするんだが……、そう思うのはまた俺が意識し過ぎなせいなのかね……。
はぁ……と、ため息混じりに膝の上の妹姫を見下ろすと。
……胸元が大きく開いたブラウスを着た珠希ちゃんの、零れんばかりの白い双丘が俺の視界に飛び込んできて――!
……胸元が大きく開いたブラウスを着た珠希ちゃんの、零れんばかりの白い双丘が俺の視界に飛び込んできて――!
「――――ッ!?!?」
ヤバい、この上なくヤバいものを見てしまったッ!
つーか割とはっきり見えたぞ!? も、もしかしてその下に何も着てないの!?
つーか割とはっきり見えたぞ!? も、もしかしてその下に何も着てないの!?
ぐっ……ま、マズい……ッ!
こんな密着した状態で“本能 ”を目覚めさせてみろ、それこそ兄の沽券に関わる……ッ!!
こんな密着した状態で“
慌てて俺は手元の参考書を目の前に広げ、数式を片っ端から頭の中に放り込む。
色即是空、心頭滅却、記憶抹消――ッ!
色即是空、心頭滅却、記憶抹消――ッ!
「? どうしたんですか、兄さま?」
珠希ちゃんがまた肩越しに振り返り、怪訝そうに問い掛けてくる。
気持ちは分かるが、今は参考書から視線を逸らすわけにはいかない。絶対にだ。
もう一度アレを見てしまったら、そこで俺の人生はジ・エンドだ……ッ!
気持ちは分かるが、今は参考書から視線を逸らすわけにはいかない。絶対にだ。
もう一度アレを見てしまったら、そこで俺の人生はジ・エンドだ……ッ!
「い、いやっ、何でもないっ。只の勉強の続きだっ」
「……そうですか。兄さまも、少し休憩にしたらいいのに」
「……そうですか。兄さまも、少し休憩にしたらいいのに」
ちょっとつまらなそうに言って、珠希ちゃんは再び俺にもたれかかる体勢に戻った。
そうして俺は、気付かれない程度に数回深呼吸をして内なる動揺を鎮める。
すぅ……はぁ……、落ち着け、俺……っ。相手は妹……、そう、この世界では妹なんだ……っ。
すぅ……はぁ……、落ち着け、俺……っ。相手は妹……、そう、この世界では妹なんだ……っ。
「このブラウス、もうお胸のところがきつくてボタンが上まで留まらないんですよね」
「だったらサイズの合った服を着てくださいお願いします!!」
「だったらサイズの合った服を着てくださいお願いします!!」
壮絶に突っ込みを入れる俺だった。
こ、この子は……っ!
分かっててやってる小悪魔なのか、それとも天然の為せる業なのか、もう全く判断が付かん!?
分かっててやってる小悪魔なのか、それとも天然の為せる業なのか、もう全く判断が付かん!?
「だって、まだ着れるのに勿体無いじゃないですか」
「そ、それはそうかも知れんが……っ、それにしたって女の子がそんな無防備な格好しちゃダメだろ!?」
「大丈夫ですよ。“こんな格好”見せるのは、兄さまにだけ……ですから」
「そ、それはそうかも知れんが……っ、それにしたって女の子がそんな無防備な格好しちゃダメだろ!?」
「大丈夫ですよ。“こんな格好”見せるのは、兄さまにだけ……ですから」
珠希ちゃんは少しだけ恥ずかしそうに、それでいてきっぱりとした口調で言う。
俺にだけ……ってのは、“家族”だから多少だらしないところを見られても平気、ってことか?
それとも“兄貴”として信用されてるってことなのか。
それとも“兄貴”として信用されてるってことなのか。
言われてみれば当たり前のことだ。
やっぱり、俺のほうが意識し過ぎなんだよな。相手は妹なんだから。
やっぱり、俺のほうが意識し過ぎなんだよな。相手は妹なんだから。
「分かったよ。でもいくら家族の前だからって、程々にな?」
「……はぁ……、……全然分かっていませんよね」
「へ?」
「……はぁ……、……全然分かっていませんよね」
「へ?」
何故か思いっきり呆れられた感じでため息をつかれたぞ?
「……俺、何か変なこと言った?」
「兄さまは、へたれってことです」
「兄さまは、へたれってことです」
…………三姉妹全員からへたれ呼ばわりされる俺って……。
くっ、なんかちょっと旅に出たくなってきた。
くっ、なんかちょっと旅に出たくなってきた。
「まあ、そういうところも兄さまらしいですけど」
「それ……一応フォローなんですかね……?」
「それ……一応フォローなんですかね……?」
がっくりとうな垂れる俺に、珠希ちゃんはくすくすと笑いながらその後頭部を俺の胸に押し当てる。
「……あ、まだお髪が濡れているから、兄さまの服が……」
「ん。ああ、別にいいよ。すぐ乾くし」
「ん。ああ、別にいいよ。すぐ乾くし」
珠希ちゃんの濡れ髪の水分を吸って俺のシャツが少し湿ってしまったが、別段気にする程でもない。
「でも……。……そうだ、兄さまっ。お髪を拭いてください」
そう言って、にこにこと首に掛けていたタオルを俺に手渡してくる。
「な、何で俺がっ?」
「昔はよくこうやって拭いてくれましたよね?」
「昔はよくこうやって拭いてくれましたよね?」
うん、確かに6歳の珠希ちゃんにはそんなことをしてあげた記憶もあるが。
「それは小さい頃の話だろっ? 今の歳になって、それは……」
「ふっ……お姉ちゃんの頭は撫で撫でできて、私のお髪は拭けないなんて、一体どういう了見なんでしょうね?」
「よしッ、任せろ!」
「ふっ……お姉ちゃんの頭は撫で撫でできて、私のお髪は拭けないなんて、一体どういう了見なんでしょうね?」
「よしッ、任せろ!」
二つ返事で快く承諾してやった。
――っていうか、いつから見ていたんだお前は!?
襖の隙間からずっと覗いていた姿を想像すると凄ぇ怖いんですけど!?
襖の隙間からずっと覗いていた姿を想像すると凄ぇ怖いんですけど!?
涙目半分、ヤケクソ半分で、わしわしと大雑把に拭いてかかると。
「ひゃん。もう少し優しくしてください」
「わ、悪い」
「わ、悪い」
即座に珠希ちゃんに駄目出しをされる。
……何ていうかもう、妹と兄というよりは、お嬢様と召使ですよね。この立場。
……何ていうかもう、妹と兄というよりは、お嬢様と召使ですよね。この立場。
仰せのとおりに、少し力を弱めてやる。……それこそ撫でるくらいに。
「……こんなもんでいいか?」
「はい……とっても、気持ちいいです……♥」
「はい……とっても、気持ちいいです……♥」
そこだけ聞けばエロゲーの台詞のようだが、無論そんな色っぽい状況ではない。
むしろ、こうしていると、お風呂上りの6歳の珠希ちゃんの頭をバスタオルでごしごしと拭いてやった光景を思い出す。
そう思うと、この膝の上で揺れる柔らかい感触も、不思議とあまり意識しなくなっていた。
むしろ、こうしていると、お風呂上りの6歳の珠希ちゃんの頭をバスタオルでごしごしと拭いてやった光景を思い出す。
そう思うと、この膝の上で揺れる柔らかい感触も、不思議とあまり意識しなくなっていた。
――どのくらいの時間、そうしてやっていただろう。
俺の胸にもたれ掛かる珠希ちゃんの重みが、段々と増してきたかのように思うと。
俺の胸にもたれ掛かる珠希ちゃんの重みが、段々と増してきたかのように思うと。
「…………すぅ……、……すぅ……」
いつの間にか、膝の上の妹姫は安らかな寝息を立てていた。
小さい頃から確かに寝つきのいい子だったが、この状況でも寝るのかよ。
でもまあ、俺も床屋で眠くなるほうだし、気持ちは分からんでもないか。
それに、何だかんだ言ってバイト帰りだったし、疲れているのかもな。
でもまあ、俺も床屋で眠くなるほうだし、気持ちは分からんでもないか。
それに、何だかんだ言ってバイト帰りだったし、疲れているのかもな。
……少しくらい寝かせておくか。
俺は慎重に体をずらし、起こさないようにゆっくりと珠希ちゃんの体を俺の座っていた座布団の上へ横たえる。
まあ、こいつは一度寝たらちょっとやそっとじゃ起きないから、そんなに気をつけなくても大丈夫だったかも知れないが。
まあ、こいつは一度寝たらちょっとやそっとじゃ起きないから、そんなに気をつけなくても大丈夫だったかも知れないが。
そして、体を冷やさないよう、部屋からタオルケットを持ってきてそっと掛けてやった。
こうして眠っている顔は、本当に子供みたいであどけないんだけどな。
この子はまるで気紛れな猫のように、天使へ、小悪魔へとその表情をくるくると変える。
まったく、本当に困った妹だぜ……色々な意味で……。
この子はまるで気紛れな猫のように、天使へ、小悪魔へとその表情をくるくると変える。
まったく、本当に困った妹だぜ……色々な意味で……。
☆
俺は、静かな寝息を立てる珠希ちゃんの横で再び参考書を広げた。
すると、10分も経たないうちに玄関が開かれる音がする。どうやらまた誰か帰ってきたようだ。
すると、10分も経たないうちに玄関が開かれる音がする。どうやらまた誰か帰ってきたようだ。
「――ただいま、兄さん」
お茶の間の引き戸を開けたのは、黒猫だった。
今日の服装は、夏コミバージョンの私服。上着は着ておらず、ノースリーブで涼しげな装い。
流石にバイトに行くのにネコミミまでは装着していないようだ。
今日の服装は、夏コミバージョンの私服。上着は着ておらず、ノースリーブで涼しげな装い。
流石にバイトに行くのにネコミミまでは装着していないようだ。
「おう、お帰り。お前も今日は早上がりなんだな」
時計は午後3時半に差し掛かろうというところ。
いつもなら帰ってくるのは夕方だから、2時間くらいは早い。
理由は訊くまでもなく、珠希ちゃんと同じだろう。
いつもなら帰ってくるのは夕方だから、2時間くらいは早い。
理由は訊くまでもなく、珠希ちゃんと同じだろう。
「ええ。……あら、珠希、寝ているの?」
「ああ、帰ってきてシャワー浴びたらここで寝ちまって。バイトで疲れてるんじゃないか?」
「ああ、帰ってきてシャワー浴びたらここで寝ちまって。バイトで疲れてるんじゃないか?」
多少端折ったが嘘は言ってないぞ?
「まったく……仕方がないわね」
小さくため息をつく。
珠希ちゃんの寝付きのよさと寝起きの悪さは黒猫も熟知しているから、無理に起こそうとは思わないようだった。
珠希ちゃんの寝付きのよさと寝起きの悪さは黒猫も熟知しているから、無理に起こそうとは思わないようだった。
「このタオルケットは、兄さんが?」
「ん? ああ、湯冷めして風邪でもひいたらあれだからな」
「……ふふっ、相変わらず優しいのね……京介」
「ん? ああ、湯冷めして風邪でもひいたらあれだからな」
「……ふふっ、相変わらず優しいのね……京介」
そう言って、穏やかに微笑む黒猫。
その暖かな笑顔に、不覚にも一瞬見惚れてしまう。
その暖かな笑顔に、不覚にも一瞬見惚れてしまう。
日向も、珠希ちゃんも、ここでは可愛い『妹』だが、やっぱり黒猫は特別だ。
可愛い『妹』ではあるが、それ以上に、大切な『恋人』でもある。
それは今はまだ、俺と黒猫だけの秘密だったりするのだが――。
可愛い『妹』ではあるが、それ以上に、大切な『恋人』でもある。
それは今はまだ、俺と黒猫だけの秘密だったりするのだが――。
「……そ、そんなんじゃねえよ。当然だろ、兄貴として」
「フフッ、そうね。気が利く『兄さま』ね」
「フフッ、そうね。気が利く『兄さま』ね」
今度はくすくすとからかうように笑う。
そうして黒猫は台所のほうへ歩いていき、冷蔵庫から作り置きの麦茶をコップに注いでこくこくと飲み干した。
そうして黒猫は台所のほうへ歩いていき、冷蔵庫から作り置きの麦茶をコップに注いでこくこくと飲み干した。
「兄さんも飲むかしら?」
「いや、俺はいいよ」
「そう。そういえば、日向は出掛けているの?」
「ああ、買い物に行ってる。でも、そろそろ帰ってくる頃じゃねえかな」
「そうなの。……それなら、先に私もシャワー浴びてこようかしらね」
「いや、俺はいいよ」
「そう。そういえば、日向は出掛けているの?」
「ああ、買い物に行ってる。でも、そろそろ帰ってくる頃じゃねえかな」
「そうなの。……それなら、先に私もシャワー浴びてこようかしらね」
使い終わったコップを手際よく洗い、お茶の間を出て行こうとする。
と、襖の前で足を止め。
と、襖の前で足を止め。
「私がシャワーから上がったら、珠希を起こしてもらえるかしら。支度をさせないといけないから」
「ん、了解」
「ん、了解」
寝起きの悪い珠希ちゃんを起こすのは、いつも俺の役目。
このあたりは、兄妹の阿吽の呼吸だ。
このあたりは、兄妹の阿吽の呼吸だ。
俺の返答に満足げに口元を緩め、黒猫はお風呂場へと向かっていった。
……言っておくが、覗かないからな?